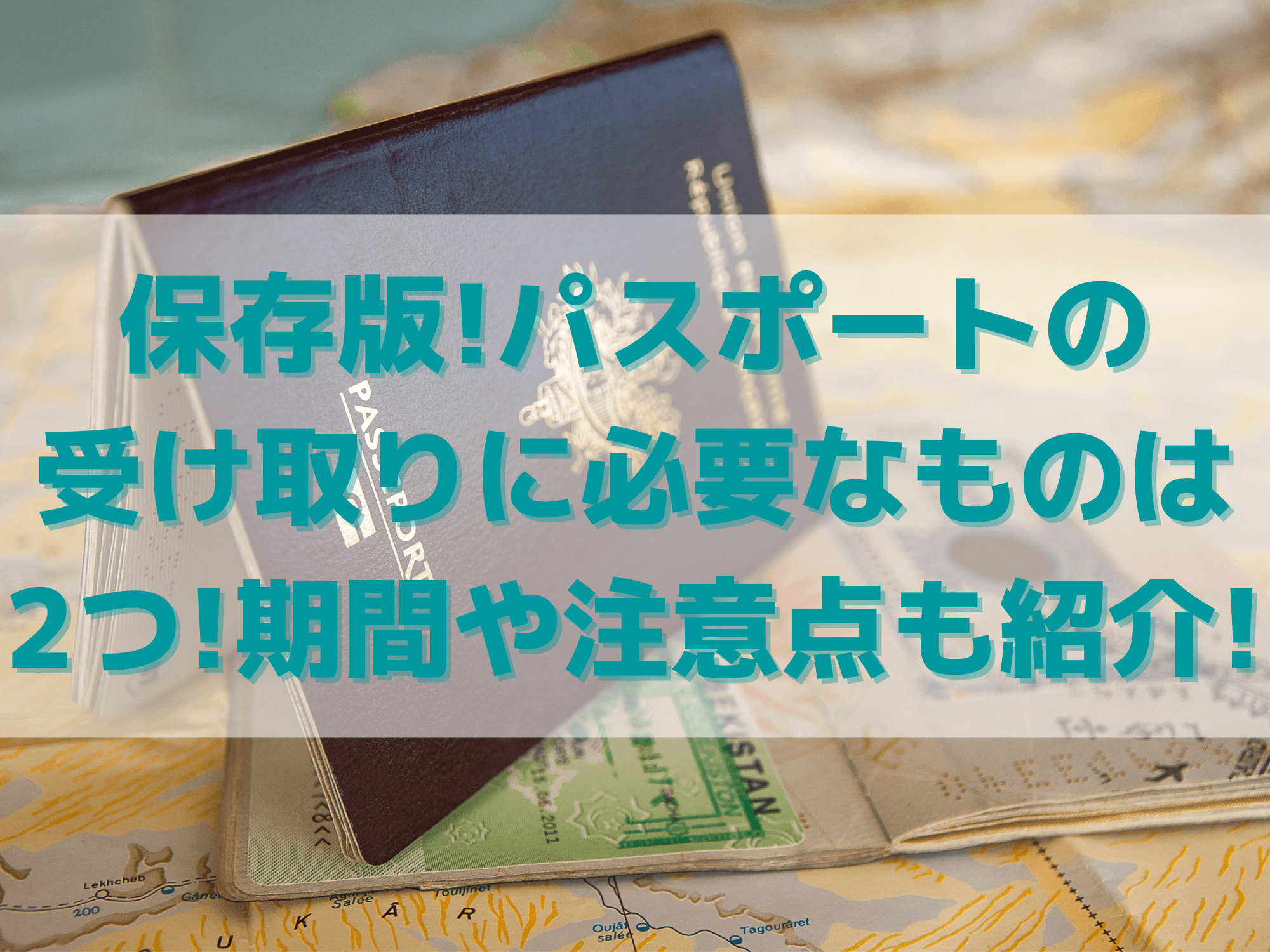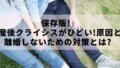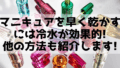「パスポートを受け取りに行きたいけど、必要なものってなんだろう?」とお困りではないですか?
パスポートの受け取りに必要なものは、申請時に渡される受領証と手数料です。
また、パスポートの受け取りは本人しかできません。
私には0歳の娘がいて、娘のパスポートを受け取りに窓口へ行きましたが、受け取れませんでした。

今回は、パスポートの受け取りに必要なものと、受け取りまでの期間や注意点を紹介します。
この記事を読まないと、私のようにせっかく窓口まで行ったのに、パスポートの受け取りができないかもしれません。
パスポートの受け取りをスムーズに行うためにも、最後までご覧くださいね!
パスポートの受け取りに必要なものは2つだけ!

パスポートの受け取りに必要なものは、パスポートを申請した時に窓口で渡される受領証と手数料です。
手数料を納める時は、現金ではなく収入印紙と収入証紙で納めます。

収入印紙と収入証紙って何が違うの?
収入印紙とは、政府に手数料などを納めるための証票で、収入証紙はパスポートの申請をした都道府県に手数料などを納めるための証票のことです。
見た目は切手に似ていて、収入印紙には金額と「日本政府」の文字、収入証紙には金額と「都道府県名」が印刷されています。
なぜ、現金ではなく収入印紙と収入証紙で納めなければいけないかというと、パスポート受け取りの際に納める手数料は、国と都道府県の収入になるからです。
パスポート受け取りの際、この手数料を納めることでパスポートを手に入れることができます。
手数料はパスポートの有効期限や年齢によって変わる
さて、パスポート受け取りの際に納める手数料ですが、申請する有効期限と、申請時の年齢によって異なります。
収入印紙と収入証紙は、パスポートセンターの窓口に売っていますが、場所によっては売ってない場合があります。
収入印紙と収入証紙はコンビニでも買えるので、パスポート申請時に窓口で売っているかどうか確認しておきましょう。
| パスポートの種類 | 収入証紙 | 収入印紙 | 合計 |
| 10年有効なパスポート(20歳以上) | 2,000円 | 14,000円 | 16,000円 |
| 5年有効なパスポート(12歳以上) | 2,000円 | 9,000円 | 11,000円 |
| 5年有効なパスポート(12歳未満) | 2,000円 | 4,000円 | 6,000円 |
お子さんのパスポートを申請する場合は、12歳になる誕生日の前々日までに申請すると、手数料が5,000円安くなります。
例えば、5/1に12歳になる場合は、前々日の4/29までにパスポートを申請すると手数料が安くなります。
必要なものは2つだけですが、どちらかを忘れてしまうとパスポートは受け取れません。
必要なものは「受領証と手数料で、手数料は収入印紙と収入証紙で納める」と覚えておきましょう。
パスポート受け取りまでの期間は申請日を含めて6日間

パスポートの申請をしてから受け取りまでの期間は、申請日と受け取り日を含めて6日間です。
ただし、土日祝日はカウントされないので注意しましょう。
参考までに、2/1にパスポートを申請した場合の例を紹介します。
| 2/1(火) | 申請日(1日目) |
| 2/2(水) | 2日目 |
| 2/3(木) | 3日目 |
| 2/4(金) | 4日目 |
| 2/5(土) | × |
| 2/6(日) | × |
| 2/7(月) | 5日目 |
| 2/8(火) | 受け取り日(6日目) |
この表のように、申請日以降に土日祝が入っていた場合は、日数にカウントされないため、受け取りは2/8になります。
私はゴールデンウィーク前に申請したため、受け取りまで10日かかってしまいました。
受け取り期間は、都道府県によって5日間のところや8日間のところもあります。
パスポートを申請する際は、受け取りまでの期間を窓口で確認しましょう。
パスポートの受け取り期間は発行日から6ヶ月以内
パスポートの受け取りは発行日から6ヶ月以内です。6ヶ月を過ぎるとパスポートは失効してしまうので注意しましょう。
私は、パスポートを申請してから取りに行くことを忘れてしまい、失効してしまったので再度申請したことがあります。
旅行の1週間前に気づき、急いで申請しましたが危うく旅行に間に合わないところでした。
私のように、申請したことを忘れてしまうこともあるので、なるべく受け取り日に窓口に行くことをおすすめします。
パスポート申請から受け取りまでの流れを知っておこう

パスポート申請の流れを把握しておくと、受け取りまでスムーズに進めることができます。
ここでは、パスポート申請の流れを紹介します。まずは必要書類を揃えましょう。必要書類は次の通りです。
- 一般旅券発給申請書 1通
- 戸籍謄本(または戸籍抄本)1通
- 住民票の写し 1通
- 証明写真 1枚
- 身分証明書
次に、パスポート申請時に必要な書類について解説します。
一般旅券発給申請書は手書きかダウンロードの2種類
パスポートを申請するには、一般旅券発給申請書が必要です。一般旅券発給申請書には手書きかダウンロードの2種類あります。
手書きの場合は、パスポートセンターの申請窓口に置いてあります。
ダウンロード申請書の場合は、外務省のホームページから必要事項を入力しプリントアウトして申請窓口に持っていきます。
私は、パスポートセンターについてから手書きの申請書を記入したのですが、申請窓口が混んでいたので、申請まで時間がかかってしまいました。
あらかじめ必要事項を入力しておいたダウンロード申請書の方が、申請窓口が混んでいてもすぐに申請できるのでおすすめです。
6ヶ月以内に発行された戸籍謄本または戸籍抄本1通
次に、6ヶ月以内に発行された戸籍謄本または戸籍抄本が1通必要です。
私は、以前市役所に行った際「いつか使うかも?」と思い戸籍謄本を発行していたので、その戸籍謄本を提出しましたが、6ヶ月を過ぎていたため申請できませんでした。
あなたも、もし家にある戸籍謄本を使う場合には、パスポートの申請をする前に6ヶ月以内かどうか確認しましょう。
また、戸籍謄本は本籍地がある市役所以外では発行することができません。
本籍地が、現在住んでいるところから遠い場合は市役所から郵送してもらうことも可能ですので、市役所に問い合わせてみましょう。
住民票と現住所が異なる場合は住民票が必要
住民票の登録地と、現住所が異なる場合は、住民票が1通必要になります。
具体的にどんなケースかというと、例えば大学に通うため東京都に住んでいるが、住民票の登録地は実家がある北海道になっている場合などです。
パスポートの申請をするために、北海道まで行くのは難しいですよね。
このように、現在住んでいるところと住民票の登録地が違う場合、住民票と賃貸借契約書や在学証明書などを用意すると、北海道まで行かなくても東京都で申請することができます。
賃貸借契約書や在学証明書以外に、追加で提出書類が必要かどうか、近くのパスポートセンターに問い合わせると不備なく申請することができます。
証明写真はパスポート用の規格に沿った写真で申請する
パスポート用の写真は必ず【縦45mm×横35mm】で申請しましょう。
証明写真機でパスポート用のサイズを選択すると、このサイズで証明写真を撮ることができます。
また、パスポートの証明写真は、カラーコンタクトレンズやディファインレンズではなく、必ずクリアレンズを付けましょう。

出国・入国審査では、瞳の色や大きさは重要な審査基準となっています。
パスポートの写真と本人の目が違う場合、別人になりすましていると疑われ、出国や入国ができなくなる場合があります。
私の友人は、パスポートの証明写真はカラーコンタクトレンズを付けていましたが、入国時はクリアレンズを付けていました。
目的地に到着すると、入国審査で審査官に本人かどうか何度も確認されたり、ボディチェックをされたり、なかなか出国できずにいました。
せっかく目的地についたのに、入国審査で足止めされたくないですよね。
パスポートの申請をする際、証明写真はクリアレンズを付けることをおすすめします。
免許証やマイナンバーカードなど身分証明書を用意する
パスポートの申請をする時は、身分証明書が必要になります。
身分証明書は、免許証やマイナンバーカード、写真付き住民基本台帳カードなどの提出が必要になります。
上記の身分証明書を持っていない場合は、①の中から2点、もしくは①と②の中から1点ずつ、確認書類を提出する必要があります。
①の確認書類は以下の通りです。この中から2点提出しましょう。
- 健康保険被保険者証
- 国民健康保険被保険者
- 証船員保険被保険者証
- 介護保険被保険者証
- 共済組合員証
- 後期高齢者医療被保険者証
- 国民年金手帳
- 国民年金証書
- 厚生年金保険年金証書
- 船員保険年金証書
- 共済年金証書
- 恩給証書
- 印鑑登録証明書と実印
②の確認書類は以下の通りです。①の確認書類の中から2点提出することが難しい場合、①と②の中から1点ずつ提出しましょう。
- 失効した日本国旅券(失効してから6ヶ月経過しているもの)
- 学生証や生徒手帳(いずれも顔写真付きのもの)
- 会社等で使用する身分証明書(顔写真付きのもの)
- 公的機関から発行された資格証明書(顔写真付きのもの)
- 母子手帳
マイナンバーカードは、マイナンバー制度が開始された時に配布された通知カードでは申請できないので注意しましょう。
必要書類を持ってパスポートセンターへ行く
次に、必要書類が揃ったら住民票の登録地にあるパスポートセンターへ行きましょう。
パスポートの申請は、配偶者(夫や妻)、二親等以内の親族(両親や兄弟、祖父母)なら代理申請が可能です。
申請書の本人記入欄が記入されたものと、先述した必要書類を提出すれば申請することができます。
代理人が申請する場合、代理人の身分証明書も必要になりますので、代理人は必ず持参しましょう。
ここまでがパスポートを申請するまでの流れです。
申請すると、受け取りの際に必要になる受領証を渡されます。
この受領証と手数料を持って、受け取り日に窓口へ行きましょう。
パスポートの受け取りには注意点が2つ!

パスポートの受け取りには注意点が2つあります。
ここを確認しておかないと、パスポートの受け取りができないこともありますので、最後までご覧ください!
パスポートの受け取りは本人のみ受け取ることができる
パスポートの受け取りは本人のみです。例えば赤ちゃんのパスポートを申請した場合、赤ちゃん本人が窓口に行かなければ親でも受け取りできません。
パスポートは日本国民ということを証明するものであり、海外に行った時に唯一国籍や身分を証明するものです。
そのため、パスポートの不正利用を防ぐために、赤ちゃんであっても受け取りは必ず本人が窓口に行かなければいけません。
お子さんのパスポートを申請した場合、必ずお子さんと一緒に窓口へ行って受け取りましょう。
申請したパスポートセンターでしか受け取りできない
注意点2つ目は、申請したパスポートセンターでしか受け取ることができないという点です。
例えば、東京都のパスポートセンターで申請をした場合、受け取りは申請した東京都のパスポートセンターでのみ受け取りできます。
パスポートは、住民票を登録している都道府県に申請を出します。
そのため、住民票を登録していない都道府県のパスポートセンターではパスポートの受け取りはできません。
この2つの注意点は、間違えやすいところなのでしっかりと確認しておきましょう。
まとめ

- パスポートの受け取りに必要なものは、申請時に渡される受領証と手数料である
- 手数料は、収入印紙と収入証紙で納める
- 12歳の誕生日の前々日までに申請すると手数料が5,000円安くなる
- パスポート受け取りまでの期間は、申請日と受け取り日を含めた6日間である。ただし土日祝は含まない
- パスポートは発行日から6ヶ月経過すると失効する
- パスポートの申請には、一般旅券発給申請書、戸籍謄本(または戸籍抄本)、住民票の写し、証明写真、身分証明書が必要である
- パスポートは本人しか受け取れず、申請したパスポートセンターでしか受け取ることができない
パスポートの受け取りに必要なものと、期間、注意点について紹介しました。
必要なものがあらかじめ分かっていれば、窓口に行ってから「受け取り出来ない!」と焦ることもありません。
パスポートの受け取りに行くときはこの記事を見て、必要なものを確認してから窓口で受け取りましょう。