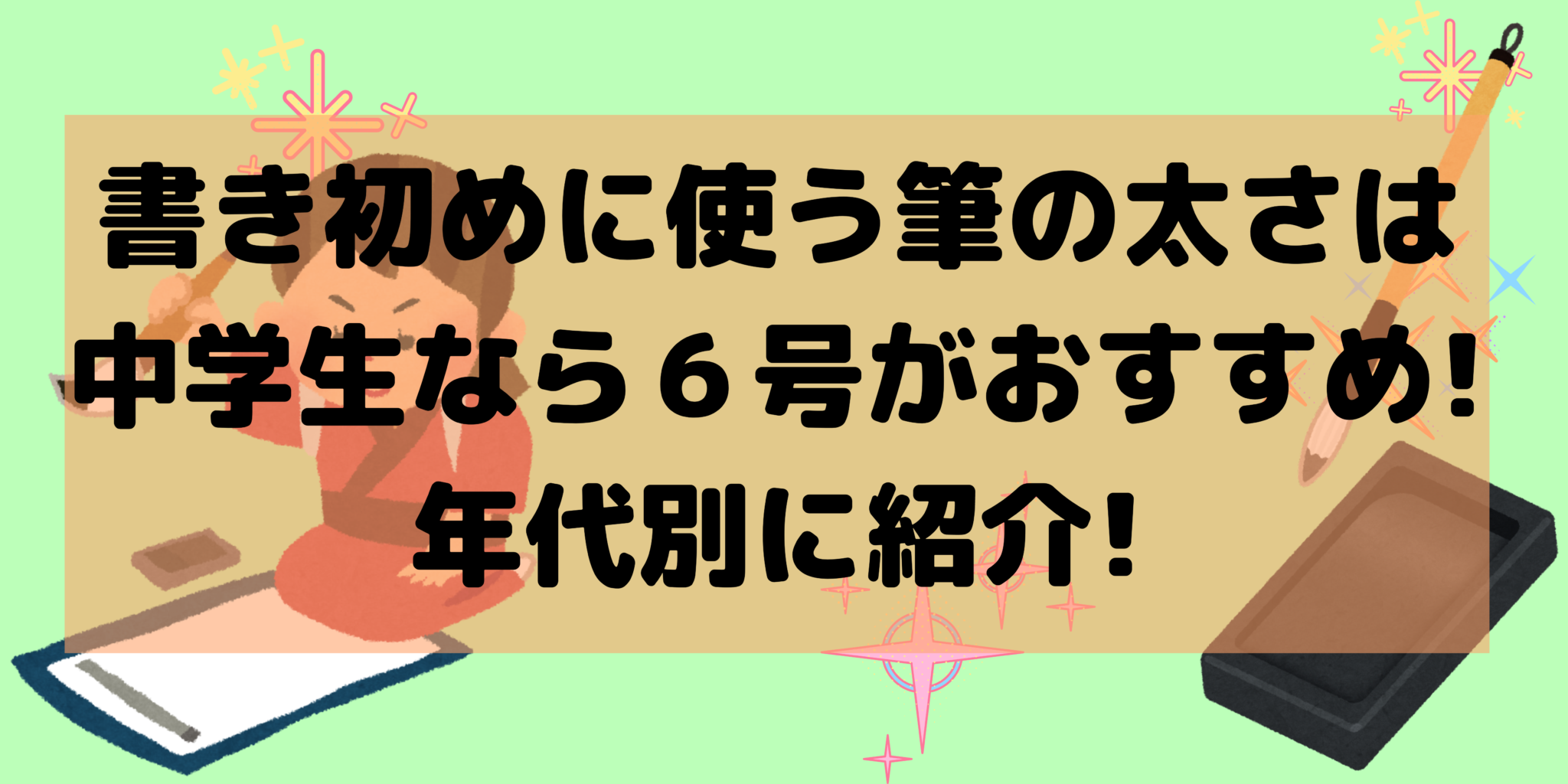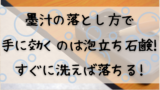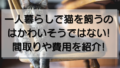小学生や中学生のお子さんがいらっしゃるそこのあなた!お子さんが書き初めでお使いになる、筆の太さ選びに困ったことはありませんか?
筆はさまざまな太さがあるので、あまり書道について詳しくないと、何号サイズを使ったら良いのか迷ってしまうと思います。
ずばり、書き初めで使う場合には、小学校低学年であれば竹軸筆の7号を、小学校高学年と中学生であれば6号のサイズを選ぶのがおすすめです。
今回は書き初めに使用するおすすめの筆の太さと、だるま筆などの筆の特徴をまとめました。
中学生なのに間違えて小学校低学年用の太さのものを買ってしまった場合、「なんか細すぎて書きづらい・・・。」となってしまうかもしれません。
そうならないためにも、ぜひこちらの記事を読んで参考にしていただき、何号を買えばいいか迷っているあなたはお子さんに合った筆選びをして下さいね!
書き初めの筆の太さは中学生であれば6号がおすすめ!

先程もお伝えしたように、書き初めに使う筆の太さは、小学校の低学年であれば竹軸筆の7号、小学校の高学年と中学生では6号を選ぶことをおすすめします。
理由は、この太さがそれぞれの体の成長に合っていて、手に持った時にちょうど良いサイズだからです。
竹軸筆というのは、書写の授業で小学生、中学生から多く使われている筆のことなのですが、この竹軸筆の号数は、筆の軸(持つところ)の太さによって決められています。
1番軸の太い筆が1号、細い筆が10号になっており、全部で10種類あります。

10種類もあるなんて、結構細かく分かれているのね…。
そして、小学校低学年が書き初めをする際におすすめする7号の軸の太さは7.6mm、小学校高学年と中学生におすすめする6号は8.5mmの太さになっています。
ここまでざっくりと、小学校低学年、小学校高学年と中学生に分けて、書き初めの際におすすめする筆の太さについてご説明してきました。
しかし、恐らく「なんかまだよく分からないな・・・。」とお思いなのではないでしょうか。

竹軸筆の号数?軸?太さは何号?よく分からない!
書道に詳しければ、「ふむふむ。そういうことね。」と感じるかもしれませんが、そうでなければ、「なんのこっちゃ」と思うことでしょう。
まずは、竹軸筆の号数についてご説明していきます。
竹軸筆の号数はどのように決められているの?
竹軸筆とは、軸が竹で出来ている筆のことです。先程もご説明したように、サイズが10種類あるのですが、それは次のように分けられています。
何号を買えばいいのか迷っているあなたは参考にしてみてください。
| 号数 | 軸の太さ |
| 1号 | 15.0mm |
| 2号 | 14.5mm |
| 3号 | 13.0mm |
| 4号 | 11.0mm |
| 5号 | 10.0mm |
| 6号 | 8.5mm |
| 7号 | 7.6mm |
| 8号 | 6.7mm |
| 9号 | 6.0mm |
| 10号 | 5.5mm |
しかし、この数値はあくまでも目安であるため、ピッタリこのサイズで作られているというわけではありません。購入する際には注意して下さいね。
書き初めの筆には違いがいっぱい!特徴を知ろう!

筆には、穂と軸と呼ばれている部分があります。書道に詳しければ聞いたことがあるかもしれませんが、そうでなければあまり聞きなじみのないワードですよね。
こちらの穂と軸にもさまざまな種類があるのですが、当然のことながらそれぞれに違いを持っています。ここではその違いについて詳しくご説明していきたいと思います。
これからご説明する違いを理解していただき、ぜひお子さんが書き初めに使う筆選びの参考にして下さいね。
穂について
穂というのは筆の毛の部分のことです。穂の長さには長峰、中峰、短峰というものがあり、穂が長いものを長峰、中くらいのものを中峰、短いものを短峰と呼んでいます。
また、穂には剛毛筆、羊毛筆、兼毛筆というものがあります。それぞれの違いは次の通りです。
〈剛毛筆〉
- 毛の色が茶色
- 馬、鹿、イタチ、タヌキなどといった動物の毛が使われている
- 弾力性に優れていて、しなやかな字を書くことができる
- 剛毛筆のほとんどのものは、同じ動物の毛から作り出られているが、中には2〜3割程度他の動物の毛と混ぜて作られたものもある
- 初心者向き
〈羊毛筆〉
- 毛の色が白色
- 山羊の毛だけを使用して作られている
- 毛質が柔らかい
- 毛が細いため、行書や草書を書くことに適している
- 墨の含みが良い
- 耐久性に優れている
- 太筆にも細筆にもよく使用されている
〈兼毛筆〉
- 剛毛筆と羊毛筆が混ざったもの
- 同じ動物の毛の柔らかいところと硬いところを混ぜた穂や、異なった動物の毛を混ぜ合わせた穂などさまざまな種類がある
- 馬、鹿、タヌキの毛の割合が多いと硬い穂になり、山羊の毛の割合が多いと柔らかい穂になる
- 初心者向き
以上が3種類の穂の違いです。お子さんが書道の経験があまりない初心者である場合は、まず、書き初めには剛毛筆か兼毛筆を使うのがおすすめです。
その後筆の使い方を徐々に身に付けていき、上達にしたら、羊毛筆へと進むのが良いでしょう。
軸について
続いては軸の説明です。軸というのは筆のもつところをいいます。
軸は大きく2種類に分けられていて、だるま軸というものと、普通軸というものがあります。この2種類の違いも見ていきましょう。
〈だるま軸〉
- 持ち手部分の軸が穂の太さに対して細くできている
- 穂が軸に対して大きいので墨の含みも良く、大きい字が書きやすい
- 小さい手でも持ちやすくなっているため、学童用の筆としても多く使用されている
- 象牙や水牛の角などを用いて高級な物もある
〈普通軸〉
- 持ち手部分の軸と穂の根本の太さがほぼ同じになっている
- 同じ穂の太さ同士で比較した時、普通軸の方がダルマ軸より軽い
以上がだるま軸と普通軸の違いです。読んでみて、どちらの軸の方がお子さんに合っていると思いましたか?
小学校の低学年くらいで、まだ手が小さい場合にはだるま軸の方が合っていそうですよね。
また、普通軸の場合は、軸と穂の根本の太さがほぼ同じになっているため、書く字を細くしたり太くしたりする調整が難しいです。
しかし、その分ダイナミックな字を書くことができます。
お子さんがもし、書道に少し慣れている場合は普通軸を使って書き初めをすると、迫力がある作品に仕上がりそうですよね。
書き初めで使った筆はお手入れをして長持ちさせよう!

筆はきちんとお手入れをしないとすぐに傷んでしまいます。あなたのお子さんは、書き初めや習字で筆を使った後、ちゃんとお手入れをしているでしょうか?
ここでは新しい筆を買った後にすることと、書き初めや習字などで使用した後に、どのようにお手入れをしたら良いのかをご説明します。
筆をおろす前に
筆は、糊(のり)で固められて売られていることが多いです。そのため、新しく筆を買っておろす場合にはその固められた糊をとる必要があります。やり方は次の通りです。
- ぬるま湯を用意する
- 筆先をぬるま湯につける
- つけながら、穂の先の方から軸に向かって手でほぐす
- 穂についていた糊が取れたら、水分をキッチンペーパーなどでよく拭き取る
- 穂を下にして吊るしてよく乾かす
この時、穂先だけをおろしたい場合にはおろしたい部分だけぬるま湯の中でほぐすようにします。
このように、穂を全部使うのか、穂先だけを使うのかによって、糊の取り方に違いがでてきます。この作業は、筆の用途をよく確認してから行うようにして下さい。
ちなみに、穂先だけを使う場合というのはどのような時なのかというと、名前書きの時です。
名前書き用の細い筆は、穂先だけをおろすのが一般的な使い方で、筆全体はおろしません。

筆を名前書き用に使う時は全部をほぐさないように気を付けよう!
以上が筆をおろす前に行う作業です。この作業を怠ると、使いづらくなるので必ず行うようにして下さいね。
使用した後は
筆を使用した後も、筆に含まれている墨をきちんと落とし、次に使う時のためにお手入れをしましょう。
使用後の墨の落とし方は、書き初めや習字をする時に使う太筆と、名前を書く時に使う細筆とで変わってきます。まずは、太筆の手入れ方法から見ていきましょう。
- ぬるま湯を用意する
- 穂の根本のあたりを丁寧にもみほぐしながら、穂に含まれた墨をとってい
- 墨が取れたら、優しく手で絞る
- 穂先を整える
- 穂を下にして吊るし、よく乾かす
これが太筆の手入れの方法です。穂に含まれた墨をきちんと全部取り切ることが大切なのですね。
では続いて、細筆の手入れ方法を見ていきましょう。
- ティッシュや半紙などに水を含ませ
- その上に穂を寝かせるようにして、穂先を整えながら丁寧に墨を落としていく
- この時、筆の糊が取れていないところをほぐしてしまわないように、注意しながら作業を行う
- 墨が全部取れたら、穂を下にして吊るして乾かす
以上が筆を使った後の手入れのやり方です。作業としては簡単ですか、お子さんがまだ小学校の低学年で小さい場合は、慣れるまでは一緒にやってあげた方が良いかもしれませんね。
筆はきちんとお手入れすると、長持ちさせることができますので、必ず行って下さいね。
書き初めをする時におすすめする筆はコチラ!

続いては書き初めをする時におすすめする筆をご紹介いたします。
あまり書き初めに慣れていない方でも使いやすい初心者向けの筆を探してみました。
これから書き初め用の筆を買いに行こうと思っている人は、ぜひ参考にしてみて下さい。
小学校低学年におすすめする筆
小学校低学年におすすめの筆は、株式会社エコール教材が販売している、「書初め筆2本セット 初心者向け書き初め筆」という筆です。
- 書初め筆2本セット 初心者向け書き初め筆

- 価格:1,417円(税込)
- 兼毛筆
- 太筆7号と細筆の2本セット
- 毛量がたっぷりあり、穂先のコシが強い
- 墨の含みが良く、扱いやすい
こちらの筆は学童用の筆ということもあり、ぜひ小学校低学年のお子さんにおすすめしたいです。
また、細筆との2本セットで税込1,417円ということでお値段もお手頃なので、初めての書き初めで筆に迷う場合は、まずはこちらの筆を試してみてはいかがでしょうか。
小学校高学年と中学生におすすめする筆
小学校高学年と中学生のお子さんにおすすめする筆は、株式会社あかしやが販売している「書初め用筆6号 人造毛書写楽」です。
- 書初め用筆6号 人造毛書写楽
- 特殊なポリエステルの毛で作られている
- 耐久性に優れており、毛が抜けにくく、また、切れることも少なく丈夫
- お手入れが簡単でまさに初心者向け
- 弾力性に優れており、穂先も鋭くなっているため、トメ、ハネ、ハライなどといった基本な点画を美しく表現することができる
こちらは動物の毛ではなくて、人造毛で作られていることが特徴です。
また、お手入れが簡単にできるというのも、初心者向けに作られていてありがたいですよね。
まとめ

- 書き初めに使用するおすすめの筆の太さは、小学校低学年であれば竹軸筆の7号で、小学校高学年と中学生であれば6号
- 竹軸筆というのは、書写の授業で小学生、中学生から多く使われている筆のことで、号数は軸(持つところ)の太さによって決められる
- 筆の毛の部分を穂といい、持つところを軸という
- 穂には剛毛筆、羊毛筆、兼毛筆があり、初心者が書き初めをする際におすすめする穂は剛毛筆か兼毛筆
- 軸にはだるま軸と普通軸があり、だるま軸は小さな手でも持ちやすい作りになっている
- 筆を長持ちさせるコツは、筆をおろす前と使用した後にきちんとお手入れをすること
- 書き初めの際、小学校低学年におすすめの筆は、株式会社エコール教材が販売する、「書初め筆2本セット 初心者向け書き初め筆」
- 小学校高学年と中学生におすすめの筆は、株式会社あかしやが販売する「書初め用筆6号 人造毛書写楽」
今回、小学生と中学生が書き初めの時に使う、おすすめの筆の太さや種類、おすすめする筆をご紹介しました。
この記事を読んだあなたの、少しでもお役に立てたのなら嬉しく思います。
ぜひこちらを参考にしていただき、お子さんの手に合っていて、書き心地が良いと思える筆を選んでみて下さいね!