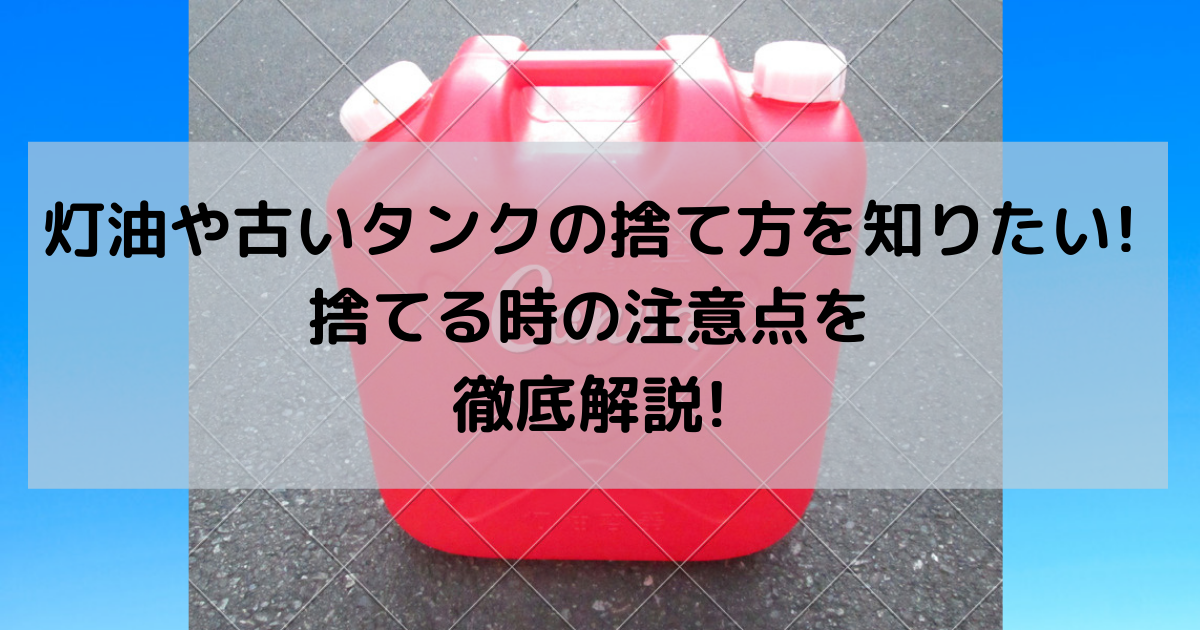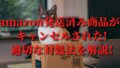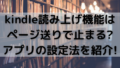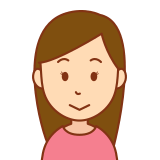
灯油が余っているけど、使い切れるかしら。
3月くらいになると、このようなお悩みを抱えるかもしれません。
実は余った灯油や古くなった灯油タンクにはきちんとした捨て方があります。
正しい捨て方を知らずに自己流で処分することは危険です。
ですので、余った灯油や古くなった灯油タンクを処分したいのであれば、それぞれの正しい捨て方を知ることが重要なポイントになるのです。
この記事ではそのあたりを詳しく解説していますので、どう捨てたら良いのか悩むことはなくなり、晴れやかな気分で春を迎えることが出来ます!
では、余った灯油の捨て方や灯油タンクの捨て方、いつもと違うおしゃれな灯油タンクのご紹介、灯油タンクの色の由来などについて、これからお伝えしていきますね。
灯油や古いタンクの捨て方とは?その方法を解説
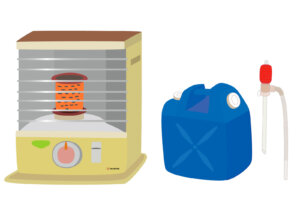
余った灯油や古くなった灯油タンクはきちんとした捨て方があります。灯油は37℃以上で引火する可能性の高い危険物質なので、正しく処分する必要があるのです。
もしあなたが、巷で流れる噂話などを聞いて自己流で捨てられているなら、これからお伝えすることをよく読んで、正しく捨ててくださいね。
余った灯油を自己流で捨てるのは、捨て方によっては環境汚染や事故にもつながる可能性があるのでやめておきましょう。
ここでは、タンク内に余った灯油の正しい捨て方と間違った捨て方、そして古くなった灯油タンクの捨て方などについてお伝えしていきたいと思います。
大量に余った灯油の正しい捨て方を知りたい!
タンク内の灯油が大量に余ってしまった場合、その捨て方には主に3つの方法があります。
●ガソリンスタンドに持ち込んで処分してもらう
タンク内に大量に余ってしまった灯油の捨て方としては、ガソリンスタンドに持ち込んで処分してもらう方法が一番簡単です。
ただ、引き取ってもらえるガソリンスタンドを探して、灯油タンクを自力で運ばなければならないので、その分の手間はかかります。
ちなみにセルフのガソリンスタンドでは、灯油の引き取りを行なっていないところがほとんどです。
とはいえ、ガソリンスタンドによっては無料で処分してもらえるところもありますし、料金がかかっても500円程度なので良心的です。
お車をお持ちで、近くに灯油を引き取ってもらえるガソリンスタンドがあれば、ただ車に乗せて運ぶだけで済むので、余った灯油の捨て方としてはお手軽と言えます。
●灯油を購入したお店に引き取ってもらう
灯油は主にガソリンスタンドに直接買いに行ったり灯油販売店から配達してもらったりして購入される方がほとんどだと思います。
ガソリンスタンドで引き取ってもらえるのですから、灯油販売店でも引き取りは可能です。灯油が余ったら購入先の灯油販売店で引き取ってもらいましょう。
ただ注意する点は、灯油を購入した時のレシートがないと引き取りが有料になってしまうかもしれないという点です。
しかし灯油を購入した時のレシートがあれば、大抵は無料で引き取ってもらえますよ!
いつもレシートは捨ててしまうという方も、灯油を購入した時のレシートは取っておくことをオススメします。
●知り合いに譲る
ご自分は使わなくても、ご近所などではまだ灯油を使われる方がいらっしゃるかもしれません。
ご自宅の灯油が大分余っているようなら、ご近所で灯油を必要とされている方がいないかどうか、尋ねてみても良いと思います。
もしそういう方がいらっしゃれば、相手の方は灯油を購入しなくても良いですし、ご自分も灯油を処分する手間がなくなりますよ。
もちろん、処分料はいらないので、お互いに良いことばかりですね。
少し余った灯油なら家でも処分できるので簡単!
灯油タンクの中の灯油が少し余ってしまった時の捨て方は、次の2つです。
●3月から6月の間に使い切る
3月くらいになると、ストーブをつけるほど寒くはありませんが、朝晩はまだ冷えることがあると思います。
といっても、これくらいの寒さでつけるのはもったいない、と感じる方もいらっしゃるかもしれません。
しかしそうやってつけないでいると、結局余らせることになります。ですのでここは使い切ってしまいましょう。
春の長雨や梅雨の時期は洗濯物を外に出せないので、乾燥機代わりにストーブをつけて洗濯物を乾かすという手段もあります。
雨の時期でも洗濯物が乾きやすくなりますし、タンク内の灯油も使い切れるので一石二鳥ですね。
●布や新聞紙などの紙に染み込ませて可燃ごみに出す
灯油タンク内に残っている灯油が100㏄ほどのごくわずかな量であれば、いらない布や新聞紙に染み込ませて捨てるという捨て方が簡単でおススメです。
ただ、自治体によっては可燃ごみで出せないところもあるので、少量の灯油の捨て方についてはお住まいの市区町村のホームページで念のため確認しておきましょう。
余った灯油の捨て方として間違った方法や考え方とは
灯油タンクの中に入っている灯油を自己流で捨ててしまうのは危険です。そしてよくやりがちな自己流の捨て方は以下の4点になります。
●凝固剤で固めて捨てる
揚げ油などの多めの使用済み油を処分するのに便利な「凝固剤」はご存知の方も多いと思います。
しかし凝固剤は、油がまだ熱いうちに薬液を溶かして混ぜて固めるものです。
ということは、灯油タンクの中に入っている常温の灯油に溶かして混ぜても灯油は固まりませんし、かと言って灯油を温めるのは発火の危険性が高いのでやめましょう。
●台所のシンクやトイレに流す
この捨て方は環境汚染につながりますのでやめましょう。また、下水管を通る時に気化して爆発する可能性もあります。
ちなみに私が住んでいる団地で、食用油を台所のシンクに捨てていた方がおり、マンホールの蓋から何か液体が爆発したように吹き出してきたことが過去にありました。
普通の油でもそのように吹き出してくるので、それが灯油だったら大爆発になるかもしれません。
「これくらいなら…」という考えはやめましょう。
●土に埋めて処分する
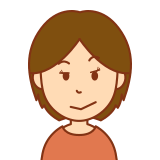
土に埋めてしまえば臭いも分からないし下水管に流れることもないから大丈夫!
そんな噂を鵜呑みにして、自宅の庭や近所のどこかの土に埋めて処分するという捨て方は土壌汚染につながります。
通常、生ゴミなどは土に埋めても微生物が分解しますが、灯油は微生物が分解することは出来ません。
灯油が埋められた土では植物などは育ちませんので、使えない土地となってしまいます。
土に埋めて、なかったことに出来るのは表面上だけで、植物や穀物などが育たないなど後々困ったことになるので、土に埋めるのもやめたほうが良いですよ。
●燃やして捨てる
灯油は37℃以上の環境におかれると、引火して燃えやすいという性質があります。その性質を利用して、燃やして揮発させようとするのは実は危険です。
かなり勢いよく燃える可能性が高いので、灯油タンクの中に入っている灯油だけを燃やすつもりが、周りを巻き込んでしまう大火事になるかもしれません。
この4点が、よくありがちな間違った灯油の捨て方になります。灯油のような危険物を素人の考えで処分しようとするのは危険ですので、やめたほうが良いと思います。
空の灯油タンクは燃えるゴミでも処分できる!
使い切って空になった灯油ポリタンクは各自治体の処分場に持ち込んでも良いですが、家庭ゴミである「燃えるゴミ」として処分するのが一番簡単な捨て方です。
ちなみに金属製の灯油タンクは「缶・金属類」として処分してもらうのが一番簡単な捨て方になりますので、指定の日に出しておきましょう。
ただ、指定ゴミ袋に入らない大きさの場合は「粗大ゴミ」になりますし、自治体によっては燃えるゴミではなく違うゴミの日に出す場合もあるので注意が必要です。
しかし大抵の自治体では、指定ゴミ袋に入れて燃えるゴミの日(金属製の灯油タンクは金属ゴミの日)に出せば持って行ってもらえます。
灯油タンクの捨て方は意外と簡単ですので、お手持ちの灯油タンクが指定ゴミ袋に入るかどうか、どのゴミの日に出せばよいのかを調べてから、正しく捨てましょう。
余った灯油は来シーズンまで持ち越せない!
灯油は時間が経つと劣化します。劣化した灯油を使用すると、ストーブに不具合が起きる可能性が高いのです。
「捨て方が分からないしまだ使えるだろうから、そのまま来シーズンまで保管しておこう」と考えて灯油を来シーズンまで保管されてはいないでしょうか?
劣化した灯油を使用することは、ストーブに火がつかなかったり爆発事故が起きたりする可能性が高いので、実は危険なことなのです。
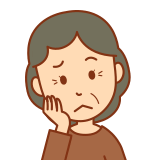
しっかりタンクの栓を閉めて、直射日光の当たらない涼しいところに置いていてもダメなのかしら?
保存状態が良くても長期間保存してある灯油は劣化します。食用油でも、栓を開けたてのものと栓を開けてから時間が経ったものを比べると、味に違いが出ますよね?
やはり一度空気に触れた灯油になると、タンクの栓をしっかり閉めても酸化が進むので劣化してしまうのです。
また、灯油タンクはプラスチック製のものがほとんどです。ポリタンクだと、中の灯油が次第にポリタンクを溶かしていくので、灯油の性質も変わってしまいます。
そうして劣化した灯油や不純物が入った灯油は「不良灯油」と呼ばれており、そういった灯油は使わないようにという注意喚起は国からもされています。
灯油の捨て方はこれまでお伝えしてきましたが、それほど難しくないと思います。
「もったいない」と思う気持ちは分かりますが、事故にでもなったらそれこそ大問題です。
事故防止のためにも、灯油は使い切るか正しい捨て方できちんと処分しましょう!
灯油タンクをおしゃれに魅せたい!人気のデザインは?

おしゃれな灯油タンクと言えば、モスグリーン系のキャンプ用灯油タンクです。
お馴染みの赤や青の灯油タンクも良いですが、古いタンクを処分するなら、次はいつもと少し違うおしゃれな灯油タンクを購入するのも良いかもしれません。
玄関に入った時、普通の灯油タンクでも冬らしさがあって良いのですが、ミリタリー調のおしゃれな灯油タンクがあると、玄関が何だかスッキリとして見えませんか?
そしてそういったミリタリー調の灯油タンクはキャンプ場など屋外で利用することを目的としているため、サイズも豊富で機能性にも優れています。
ではオススメのおしゃれな灯油タンクについて、これから説明していきますね。
おしゃれ灯油タンクといえばやっぱりミリタリー調!
ミリタリー調といえば、迷彩柄やモスグリーン系を思い浮かべる方も多いと思います。
そしてそんなミリタリー調の代表格とも言えるのが、「ヒューナースドルフ フューエルカンプロ」というドイツ製の灯油タンクです。
オリーブ色の本体に給油ノズルが収納できるようになっており、スッキリとした四角い形でとてもおしゃれな感じがします。なんとスタッキングも可能です。
この灯油タンクの魅力は、ミリタリー調の色はもちろんのことですが、給油ノズルが本体に収納できることです。
通常の灯油タンクだと、給油ノズルは別売の給油ノズルケースを購入するか、灯油タンクに立てかけておくかのどちらかになりますよね。
もしかしたら、給油ノズルケースは場所を取るからといって灯油タンクに挿しっぱなしにしてはいませんか?
給油ノズルを挿しっぱなしということは、灯油タンクの栓は常に空いているので空気に触れて酸化がどんどん進んでいってしまいます。
実は私も給油ノズルを壁と灯油タンクの間に挟み込んでいたり挿しっぱなしにしていたりした時期がありました。
しかしこの「ヒューナースドルフ フューエルカンプロ」であれば、そんなお悩みも解決できます。
サイズは5L、10L、20Lとあるので、試しに5Lを購入してみて、使い勝手が良ければ、20Lを購入するというようにしてみても良いですよね。
ただしお値段は20Lで5500円くらいかかります。通常の灯油タンクの3倍近くのお値段なので、購入するのに少々勇気がいるかもしれません。
それでもインテリアの一つとして考えてみればいかかでしょうか?玄関がそれ1つでおしゃれに見えるなら、購入してみても良さそうです。
新しい家具を購入するつもりで、お一ついかがですか?
お手頃価格のおしゃれな灯油タンクが欲しい!
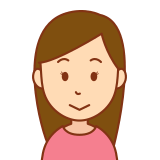
おしゃれなミリタリー調で値段がお手頃な灯油タンクはないかしら?
そんなお悩みを持っているあなたには、「瑞穂化成 扁平缶 ノズル無し20L」がオススメです。
お値段は2000円弱なので、通常の灯油タンクとそんなに変わりはなくお手頃価格になっています。
ただ残念ながら給油ノズルを収納出来る場所はついていません。
しかし「見た目だけでもおしゃれ感が欲しい!」という方にはピッタリの灯油タンクになります。
こちらのメーカーは、小さいサイズですと4L、10Lがあります。
色も、モスグリーンやグレー系などカラーバリエーションは豊富にあるので、「おしゃれでお手頃価格の灯油タンクが欲しい」という方にオススメです。
おしゃれさと機能性を兼ね備えた灯油タンクといえば?
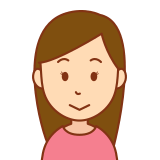
20Lだと運ぶのが重くて大変…。
そんなお悩みをお持ちのあなたには、「タンゲ化学工業 カラータンク 2000GT 」がオススメです。
こちらの灯油タンクは、何と車輪が付いていて持ち運びがとても便利なので、女性の方にも人気が高いようです。
見た目は「赤」ですが、パッと見た感じはお馴染みの灯油タンクとは違い、小さいスーツケースのようでおしゃれ度が増しています。
ただ残念なことに、こちらも給油ノズル付きではありません。
しかし持ち運びに不便を感じていて、いつもの灯油タンクとは違うおしゃれなものが欲しいというあなたにオススメです。
お値段も3000円弱なので、通常の灯油タンクと比べてみてもそれほど変わりはありません。比較的お手頃価格と言えるでしょう。
それにしても、赤や青の灯油タンクや緑やグレーの灯油タンクなど、灯油タンクの色だけでも随分と印象が変わるものですね。
同じ赤でも形が違うだけでおしゃれに見えるなど、物の色や形は印象を大きく変えます。
いつもの赤や青の灯油タンクが、いわば素顔だとしたら、緑やグレーなどの灯油タンクや車輪付きの灯油タンクは、さしずめお化粧をした外用のお顔と言えますね。
素顔の灯油タンクのままでも充分ですが、外用に仕上げられた灯油タンクは何だか一味違って見えるものです。
灯油タンクは玄関に置かれる方も多いと思いますので、玄関をおしゃれに見せるために、こういったおしゃれな灯油タンクを置いてみるのも良いかもしれません。
灯油タンクは使いやすさと安全性を重視して選ぶ
おしゃれな灯油タンクを購入する時は、使いやすさと安全性を重視して選ぶことが重要なポイントになります。
例えばお車を持っていらっしゃらなければ、出来るだけ手軽に運びやすい10Lサイズの灯油タンクが良いと思います。
しかし10Lで大体灯油ストーブのタンク一回分ですので、頻繁に灯油を買いにいかなければなりません。
何回も行くのが面倒なあなたは、車輪付きの灯油タンクが良いでしょう。
また、ワンルームマンションにお住まいであれば、玄関はあまり広めに設計されていないので、コンパクトでスリムな形の灯油タンクが良いと思います。
そして安全性の高さという点で言えば、「JISマーク付き」もしくは「メーカー保証付き」のものを選ぶことが重要なポイントです。
JISマークは、簡単に言えば品質を保証された安心マークのようなものなので、このマークがついていれば安心と言えます。
また、JISマークがついていなくても、ヒューナースドルフのようにドイツの製品安全基準TUVという認証を受けているものもあります。
これがいわゆる「メーカー保証」というものです。
以前にもお伝えしたように、灯油は危険物質ですので、使いやすさと見た目の良さだけではなく「安全性」を十分に考慮する必要があるのです。
「使いやすさ」と「安全性」ということを考えて灯油タンクを選ばれると、納得のいく灯油タンクがきっと手に入りますよ。
灯油タンクに色がついているのは何故?白ではない理由

実は、白の灯油タンクはあまり好ましくないとされています。
通常、よく見かける赤や青のタンク、その他のオシャレ灯油タンクなど、灯油タンクには色がついているのが当たり前のような認識になっていますよね。
そして、白の灯油タンクでも規定を満たしていれば問題はありません。使われている方もいらっしゃると思いますので、そこはご安心ください。
それでも、白の灯油タンクが好ましくないとされている理由は、「色の濃さ」にあります。
実は灯油は紫外線に弱く、色が薄い「白」だと紫外線から守られないため変質してしまうという性質があるのです。
変質してしまった灯油は不良灯油になってしまいます。不良灯油がストーブの爆発事故などの原因になるということは以前にお伝えしましたよね。
ですので、ある程度遮光性のある「赤」や「青」、その他色付きの灯油タンクが主流であるというわけです。
また、灯油タンクの色はお住まいの地域によっても違ってきます。なぜそうなるのか、これから説明していきますね。
灯油タンクの色は関東と関西で違う!その理由とは
通常の灯油タンクの色は、関東・甲信越や東北地方では「赤」、北海道や中部から西の関西地方、九州地方では「青」が主流です。
理由としては、関東から東北地方では「赤は危険」という意味合いを含めて、危険物である灯油を赤のタンクに入れているようです。
消防車や救急車のサイレンの色が赤なので、「赤は危険」という固定観念を利用してのことだと思います。
ではなぜ関西地方では「青」タンクなのでしょうか?消防車や救急車のサイレンの色は全国共通のはずなのに、なぜ?と思われたあなたにお伝えします。
なぜ「青」なのか?それは赤の顔料よりも青の顔料のほうが安かったからなのです。
実は昔は白の灯油タンクが使われていることが多かったのですが、それが安全性の観点から色付きの灯油タンクに切り替わった際、色を塗り替えることになりました。
その際、赤に塗り替えるよりも青に塗り替える方が安く済んだので、関西では青の灯油タンクが主流になったそうです。
なんとも関西人らしい、きっぱりとした理由ですよね。確かに安い方が良い、その気持ちよく分かります!
まとめ

- 余った灯油や古くなった灯油タンクには正しい捨て方がある
- 余った灯油は来シーズンには持ち越さない
- ガソリンスタンドに持ち込んで処分してもらう捨て方が一番簡単
- 少し余ったくらいの量なら家庭でも簡単に処分できる
- 余った灯油を自己流で捨てるのは危険
- 空になった灯油タンクは燃えるゴミとして処分できる
- おしゃれな灯油タンクと言えばミリタリー調
- 灯油タンクは使いやすさと安全性が重要なポイント
- 灯油は紫外線に弱いため白の灯油タンクはあまり好ましくない
- 関東では赤の灯油タンク、関西では青の灯油タンクが主流
余った灯油や古いタンクの捨て方は意外と簡単なので、自己判断でむやみに処分しようとしたりするのはやめておきましょう。
ストーブの時期が終わりになる時期には余った灯油は今のうちに使い切り、来シーズンに向けて灯油タンクもイメージチェンジしてみても良さそうですね!