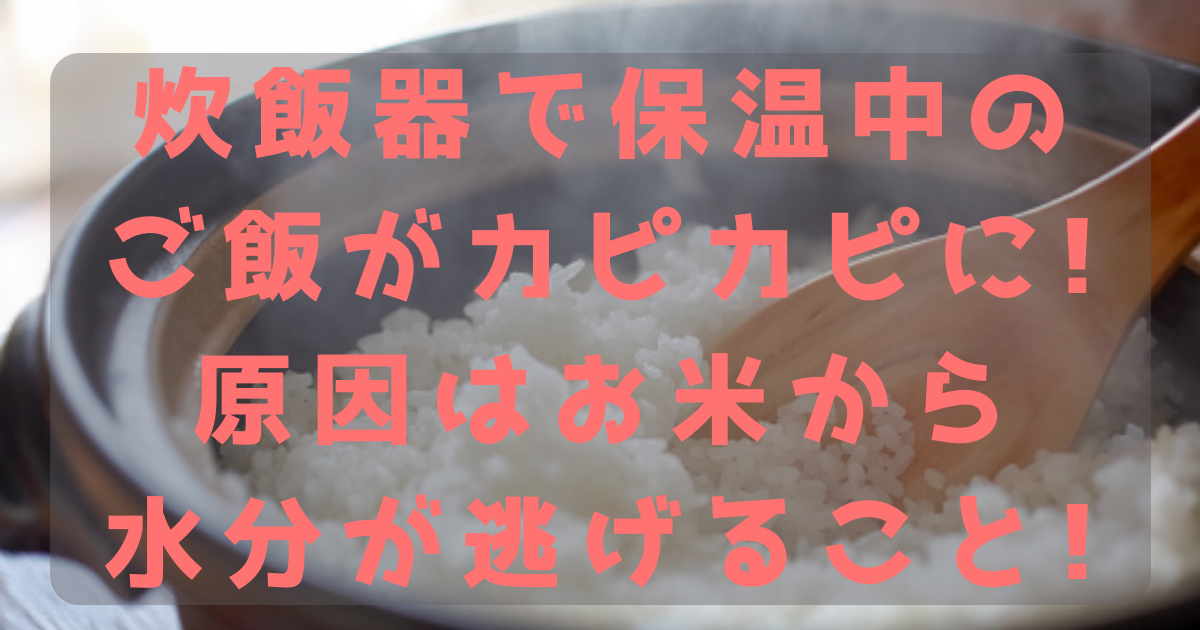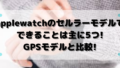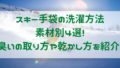ちょっとだけ保温しておこう、と思って忘れてしまったとき、カピカピのご飯をみると悲しくなるよ。

あれってどうしてカピカピになるんだろう?カピカピになったらどうしたらいいんだろう?
炊飯器でご飯を炊いて保温していたら、カピカピになってる…。こういうときショックですよね。
ご飯がカピカピになるのは炊飯器の保温により、お米から水分が逃げてしまうためです。
長時間、保温機能を使うことで、カピカピのご飯になってしまいます。
この記事では、炊飯器の保温機能でご飯がカピカピになる3つの原因と、どうしたら防ぐことができるのか、について説明していきます。
また、カピカピになってしまったご飯を復活させる方法や、カピカピご飯のアレンジ方法についてもお伝えしますね。
炊飯器で保温したご飯がカピカピに!原因は3つ!

炊飯器の保温機能でご飯がカピカピになるのは「長時間の保温」「ご飯のほぐし不足」「内釜パッキンの劣化」が原因です。
なかでも「長時間の保温」をすることで、お米から水分が蒸発してしまいます。
また、ご飯のほぐし不足で水分のむらができたり、内釜のパッキンが劣化して水分が蒸発したりすることもカピカピご飯につながるのです。
この3つの原因について詳しく説明していきますね。
長時間の保温
ご飯を暖かいまま保存できる、炊飯器の保温機能ってとても便利ですよね。
ですが、長時間保温することで、ご飯に熱がずっと加わります。
その間、どんどん水分が抜けてしまうのです。
つまり保温時間が長くなればなるほど、ご飯はカピカピになってしまいます。

長時間保温をしていると、お米が黄色くなることがあるけど、あれはどうしてなの?食べても大丈夫?
ご飯は炭水化物でできていますよね。炭水化物には糖分とアミノ酸が含まれています。
その糖分とアミノ酸が加熱されることによって、メラノイジンと呼ばれる物質が作られるのです。
このメラノイジンと言う物質は、褐色系の色をしています。そのためご飯は炊飯器で保温すると黄色くなることがあります。
黄色くなったご飯を食べても体に害はありません。
ですが、黄色いご飯はあまりおいしそうに見えないですよね。
ご飯がカピカピにならない方法を試すことで、黄色くなることも防げますよ。
ご飯のほぐし不足
ご飯のほぐし不足も、ご飯がカピカピになる原因の1つです。
炊き立てのお米には表面に水分がついています。
それをほぐさず保温していると、ふやけたお米同士がくっつき、保温効果でそのまま固まってしまうのです。
しっかりほぐすことで、水分が分散されて、余分な水分がとんでくれますよ!
そのため、お米は炊けたら、少し蒸らしてからしっかりほぐしておきましょう。

混ぜない方が美味しいって聞いたことがあるけど…。
確かに、混ぜない方が粘りと甘みが出て美味しい、という意見もあります。
そこは好みの問題です。混ぜないご飯が好きな場合は、炊き立ての一膳目はそのまま食べて、そのあとはしっかりほぐすといいでしょう。
内釜パッキンの劣化
炊飯器の不調と言うのは、内釜のパッキンが劣化している場合をいいます。
内釜のパッキンが劣化してしまうと、しっかり密封ができません。
そのため、密封できていない部分から水分が逃げてしまい、ご飯が硬くなってしまいます。
一般的に内釜パッキンの寿命は2~3年程度です。炊飯器は5年前後と言われているため、内釜パッキンだけ買い替えるといいでしょう。
取り扱いについては各メーカーに聞いてみてくださいね。
「長時間の保温」「ご飯のほぐし不足」「炊飯器の不調」に気を付けることで、水分の蒸発を防ぐことができます。
保温したご飯を少しでも長く美味しく食べることができますよ。
炊飯器の保温にご飯はいつまで入れていいの?
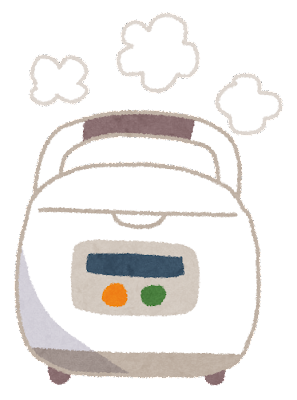
炊飯器の保温機能は、基本的に12時間から24時間が目安と言われています。
あくまでも目安で、いつまでという決まりはありません。
ですが、時間が経つほど味は落ちてしまいます。そのためいつまでと言わず、なるべく早めに食べましょう。
炊き立てのご飯の美味しさを保てるのは6時間程度と言われています。
ご飯を美味しく保つ方法について紹介しますね。
- 炊飯器のご飯の上に保温保湿シートを置く
- 炊飯器の真ん中にご飯を集めて保温する
- 冷凍する
- ご飯をおひつに入れる
これらの方法の詳細とポイントを説明します。
炊飯器のご飯の上に保温保湿シートを置く

ご飯を保温する際に、市販の保温保湿シートを置くだけです。
これはシートを置くことで蒸気が逃げるのを防いでくれます。
こちらの「おいシート」という商品はお昼の情報番組でも取り上げられていました。
ご飯の上に置くだけでパサつきと変色を予防してくれます。
今は製造終了となってしまいましたが、Amazonや楽天などで購入することができますよ。
炊飯器の真ん中にご飯を集めて保温する
炊飯器の保温機能を使うと内釜に触れているお米からカピカピになってしまいます。
そのため、内釜に触れないよう真ん中に集めることで、お米がカピカピになることを多少遅らせることができるのです。
上記2つの方法は、これをやれば絶対にカピカピにならない!というものではありません。
あくまでもカピカピになりにくい、程度だと思ってくださいね。
ご飯を冷凍する
ご飯は冷凍することで長持ちします。またレンジで解凍したときもふっくらしたご飯を楽しむことができます。
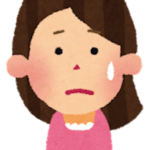
ご飯を冷凍するといいなんて知ってるよ。余ったご飯をラップで冷凍するだけでしょ?
普通に冷凍するだけでは、美味しさは半減してしまいます。
美味しくご飯を冷凍する3つのポイントをお伝えしますね。
- 冷凍するのは1膳分
- 炊き立てを冷凍する
- 1ヶ月以内に食べる
というのがポイントです。炊いたご飯は冷めていく過程で味が落ちていくと言われています。

我が家では多めに炊いておいて、炊き立てを食べたらすぐに1膳ずつラップに包んで冷凍しているよ。そうすることで、ご飯を炊く回数も減って、いつでも美味しいご飯が食べられるようになったよ!
一番美味しい炊き立て、つまり温かいうちにご飯を冷凍させましょう。
このとき量が多すぎるとレンジで温める際にムラができてしまいます。
そのため1膳くらいをラップに包んで冷凍するのがおすすめです。
ご飯をおひつに入れる
ご飯をおひつに入れることで、殺菌作用や調湿効果が得られます。
そのため翌日までごはんを美味しく食べることができますよ。
また、おひつに入れて食卓に置いておくことで、おかわりのたびに炊飯器まで行かなくていいというメリットもあります。
いつまでも炊飯器に入れておくより、冷蔵庫で冷凍したり、おひつに入れたりする方が、ご飯を美味しく保存できますよ。
また最近では長時間保温をしても、ご飯がカピカピになりにくい炊飯器が販売されています。
炊飯器の調子が悪い、買い替えを検討している、などの場合はこれらの機能も含めて検討すると良いでしょう。
まだ買い替え時期でない場合は上記の方法を試してみてくださいね。
炊飯器で保温したご飯を美味しく食べるおすすめの方法

炊飯器で保温していたご飯がカピカピになってしまった場合、失われた水分を補ってあげましょう。
炊飯器の中でカピカピになってしまったご飯に水をかけて、もう一度保温するとふっくらしたご飯にもどります。
そのときの保温時間は30分くらいがいいです。
かける水分はご飯1膳につき小さじ1杯程度にしましょう。
かけすぎるとべちゃべちゃしたご飯になってしまいます。
まんべんなく水分をかけるのに霧吹きなどを使うのもおすすめです。
すでに炊飯器からお茶碗によそったご飯は、同じように水分をかけて、レンジでチンしましょう。
レンジでチンするのは600Wで30秒~1分程度をおすすめします。
一度カピカピになってしまったご飯を食べるのはちょっと…。というあなたはいっそアレンジしてしまいましょう♪
おすすめのアレンジメニューは、チャーハンやお茶漬けやリゾットです。
お茶漬けやリゾットなど水分がたっぷりのメニューだとカピカピご飯が気になりません。
また、反対にチャーハンのように水分がなくパラパラしたメニューにもぴったりです。
ここでリゾットの作り方を説明します。とても簡単にできますよ。
- カピカピご飯 2膳
- ベーコン 2枚
- 玉ねぎ 1/2個
- 好きなきのこ(エリンギ、しめじなど) 適量
- 塩コショウ 少々
- ピザ用チーズ ひとつかみ
- バター 適量
- ◎水 100ml
- ◎牛乳 200ml
- ◎固形コンソメ 1つ
- カピカピになったご飯を軽く水で洗う
- 玉ねぎは粗みじん切り、ベーコンは1㎝程度に切る
- フライパンにバターを熱して、玉ねぎとベーコンときのこを炒める
- 水気を切った1のご飯と◎の材料を入れる
- ひと煮たちさせて、水分がとんできたらチーズを加える
- 最後に塩コショウで味をととのえる
リゾットは難しそうなイメージがあったのですが、作ってみるととても簡単です。
その割に手が込んでいるようにみえるので、我が家ではちょっと特別なディナーに作ったりもします。
エビを入れて海鮮リゾットにしたり、トマト風味にしたり、お気に入りの味を見つけるのも楽しいですよ♪
工夫することでカピカピご飯が簡単でおしゃれなメニューに大変身しますね。
まとめ

- 炊飯器で保温したご飯がカピカピになるのは、長時間の保温、ご飯のほぐし不足、炊飯器の不調が原因
- 炊飯器の保温機能を使用するのは12~24時間、美味しく食べたいのであれば6時間まで
- 炊飯器の保温機能でカピカピになったご飯は水分を補うことである程度復活する
- 炊飯器の保温機能でカピカピになったご飯はリゾットやお粥にするとおいしく食べられる
炊飯器で保温したご飯がカピカピになりにくい方法や、カピカピになった場合は以上の方法を試してみてください。
美味しくお米を食べるには、保温機能に頼り過ぎないのがいいですね。