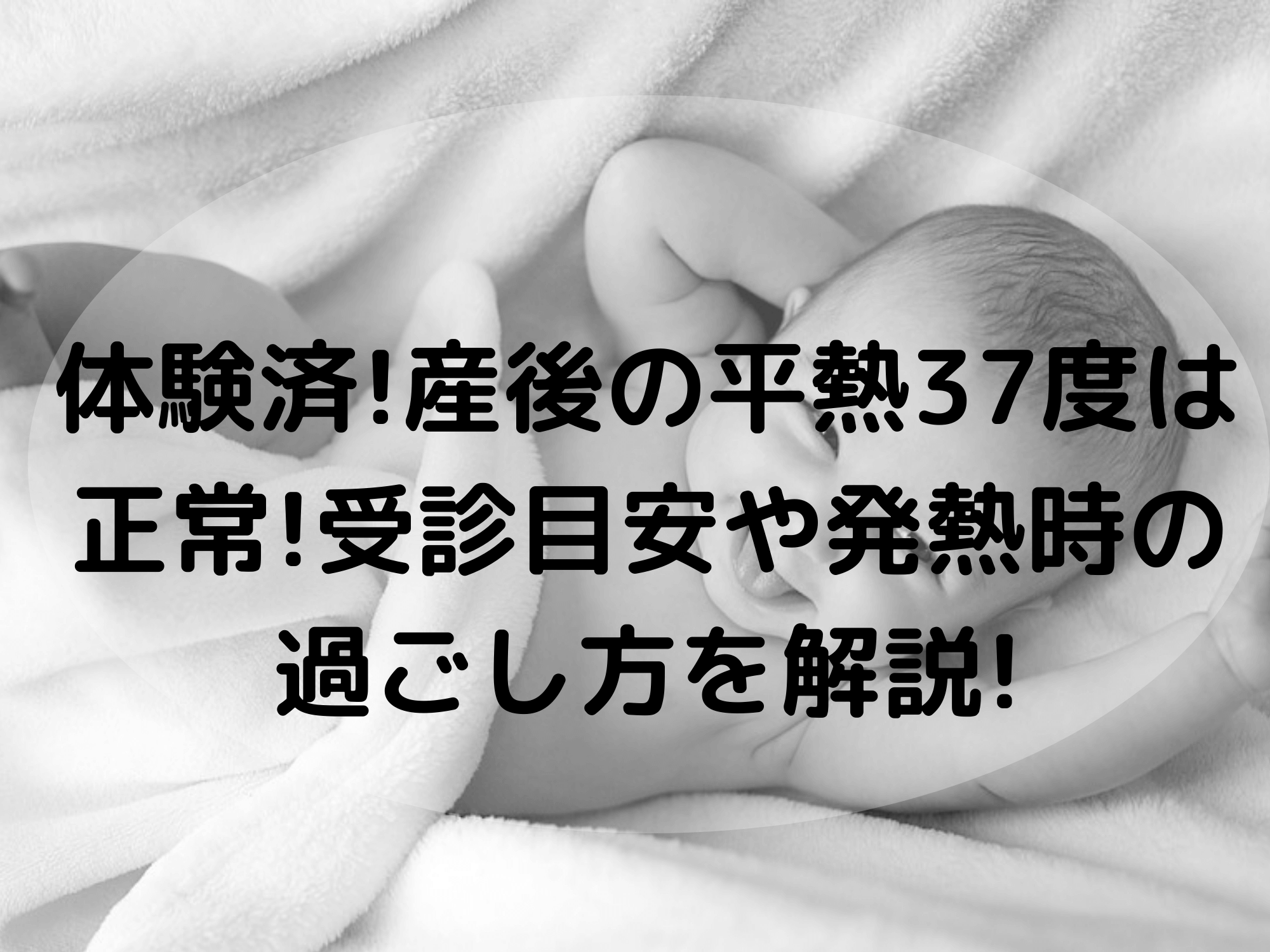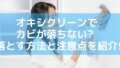出産が終わるといよいよ育児が始まります。妊娠で変化した体は軽くなり、妊娠前の体をイメージするかもしれません。
ただ10ヶ月かけて変わってきたものや、出産でのダメージは大きく、無理は禁物です。
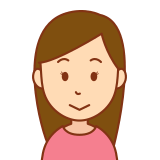
産後の平熱が37度で少し高めだけど、風邪かな?
平熱が37度といつもより高いと心配ですよね。しかも産後だと体調の変化にデリケートになります。
結論をいいますと、産後直後の平熱はだいたい37度台です。これが正常とも言えます。
ここでは、産後の平熱の変化と、産後の体調の見極め方や、過ごし方を解説します。
赤ちゃんとの生活で後回しになりがちな母体に気を配ってあげないと、赤ちゃんにとっても好ましくない状態に陥る場合があります。
赤ちゃんとの素敵な育児ライフを送るために、どうぞ最後まで御覧下さい。
産後の平熱が37度!!産後は体温が変化する!

まず出産後2週間程度、37度台の熱が出ます。これは、出産時の疲労や、出産時にできた傷が原因と考えられており、平熱38度を超えないのが正常な反応です。
わたしは2度出産していますが、産後病院では定期的に体温計測の時間がありました。
そのとき出産前の平熱より多少高かったのですが、助産師さんがなにも言わなかったのは、それが正常だからですね。
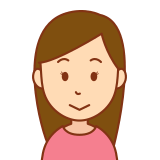
37度あっても、風邪のようなダルさはなかったな~
また、産後平熱自体が高くなるという人もいるようですが、37度台であれば様子をみてよいでしょう。
産後の平熱が高いと危険!病院受診の目安をご紹介!

この時期に発熱が38度以上と高いことや、平熱でも発熱以外の症状がある場合には注意が必要です。
場合によってはすぐに受診が必要な可能性がありますので、注意が必要な症状を紹介いたします。
38度の発熱や下腹部の違和感がある産褥熱
38度以上の高い発熱や下腹部の張りや痛み、もしくは悪臭のする悪露が出ている場合は産褥熱です。
悪露とは出産後から起こる子宮内膜や分泌物の排出で、生理よりも量が多い出血があります。
また分娩時に残った胎盤の一部が排出されることもあるため、固形のものが排出される可能性もあります。産後すぐから1ヶ月前後まで続くことが多いです。
治療が遅れると細菌が血液内に侵入増殖し、全身感染症となって敗血症を引き起こすことがあります。命に関わる病気ですので早めに受診しましょう。
<原因>
出産の際に細菌が腟や子宮に入り、感染することで起こります。(子宮内膜炎)
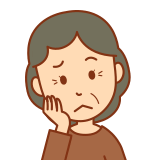
どうして細菌が感染してしまうの?
破水後24時間以降のお産や帝王切開術、胎盤遺残、母体の免疫力低下などが原因として考えられます。
また、糖尿病の合併や、性感染症の合併、悪露の流出を妨げるような筋腫があると、産褥熱を発症しやすくなります。
<治療法>
抗菌剤によって治療し、子宮内に胎盤などが残留していると重症になるので、速やかに取り除く必要があります。
乳房の腫れや部分的な熱感が見られるうっ滞性乳腺炎
うっ滞性乳腺炎は分娩後1週間以内によく見られますが、発熱はありません。
乳房の腫れ、部分的な熱感、赤みなどの症状が現れて、脇下のリンパ節が腫れることもあります。初産婦に多くみられます。
乳腺炎には、急性と慢性の2種類あります。産後授乳などにより、起こるのは、急性の方がほとんどです。
急性には、乳汁が乳管内に溜まってしまい起こるうっ滞性乳腺炎と、うっ滞性乳腺炎の症状に、感染が加わって起こる急性化膿性乳腺炎があります。
うっ滞性乳腺炎は平熱でも起こりうりますし、なりかける人も多くいるので注意が必要です。
<原因>
出産後に乳汁が乳房にたまり、炎症を起こします。母乳の通り道である、乳管が十分に開いてないことや、赤ちゃんの母乳を吸う力が弱いなどが原因です。
<治療法>
乳房をよくマッサージして、乳汁の流れを良くするのと、積極的に授乳をして赤ちゃんによく飲んでもらいます。
授乳の方法も重要ですので、赤ちゃんの抱き方を横抱きだけでなく、フットボール抱きや、縦抱きにしてあげてみましょう。
授乳前には乳頭をマッサージして柔らかくしておくと、赤ちゃんが深く吸い付きやすくなりますよ。
飲み切らずに余ってしまった場合は、搾乳するなどして、乳房に乳汁が溜まらないようにしましょう。
しかし、絞りすぎてしまうと、体がもっと母乳が必要なんだ!と勘違いし、たくさん作られてしまうので、絞りすぎには注意が必要です。
また、バランスの良い食事と休息を取りましょう。チーズや生クリームなど、脂質の高いものはNGです。
出産はお祝い事なので、ケーキなど頂くかもしれません。嬉しさのあまりパパが買ってくる可能性もあります。事前に伝えておくか、少し食べるにとどめておきましょう。
1番は和食が良いと言われています。私も、豚汁をたくさん作って食べていた思い出があります。
豚汁にはお野菜をたくさん入れて、おまけにお肉も入っているので、それにおにぎりだけで、栄養バランスがいいお昼になりました。
産後はなかなかお料理する時間も体力もないので、作り置きで工夫するのが良いかもしれないですね。豚汁作りをパパにお願いしましょう!
うっ滞性乳腺炎がひどくなると起こる急性化膿性乳腺炎
うっ滞性乳腺炎が重症になってくると、急性化膿性乳腺炎になる可能性があります。
急性化膿性乳腺炎は倦怠感があり、高い熱が出ます。乳房の痛み、しこり、腫れ、赤み、熱感、全身の震えや悪寒の症状が現れます。その後乳房に膿のかたまりができます。
<原因>
乳管や乳頭にできた傷から、細菌(連鎖球菌や黄色ブドウ球菌)が感染して炎症が起こります。
<治療法>
授乳は中止して、抗生物質や解熱鎮痛剤で治療しますので、病院へ行きましょう。膿のかたまりができている場合は切開して、取り出します。
実はわたしも乳腺炎になりかけました。乳房がカチカチになり触れるだけで痛かったです。
赤ちゃんにたくさん吸ってもらうことが大事なので、授乳も痛かったのですが、カチカチになっている部分から押し出すように授乳しました。
乳腺炎になると、本人は寝るのも辛いですし、授乳も辛いものになってしまいます。
また急性化膿性乳腺炎になってしまうと授乳も中止せざるを得なくなってしまいます。
そうなる前に軽度なうちに、病院へ行き専門家にみてもらいましょう。
排尿する時に痛みがある腎う腎炎
腎う腎炎は37度以上の発熱、側腹部痛、全身倦怠感、排尿痛といった症状があります。出産に伴い、膀胱炎や腎う腎炎になる可能性が高まります。
<原因>
細菌が膀胱から感染することで、出産後に発症する可能性があります。
感染は、妊娠中の無症候性細菌尿から始まることや、まれに分娩中または分娩後に行われる膀胱カテーテル挿入によって起こってしまうのです。
膀胱炎がこじれて腎臓まで菌が侵入すると、腎う腎炎と呼ばれる病気となります。
<治療法>
腎う腎炎は抗菌薬で早期に治療が可能です。そのため膀胱炎の症状に加えて熱が出た場合はすぐに医療機関を受診が必要です。
出産直後は膀胱炎になりやすいので、産後は特にしっかりと水分をとって膀胱炎にならないように対策してください。
調べていくなかで、熱がある場合はもちろん、平熱でもその他体に異常がある場合には、医師の診断が必要だと感じました。
生まれたての赤ちゃんがいると、自分のことが後回しになってしまいがちですが、自分のためにも、赤ちゃんのためにも、早くに専門家に相談しましょう。
産後の平熱は受診を決める目安!産褥期の過ごし方!

分娩が終了すると、元の非妊娠時の状態に戻ろうとします。この6週~8週までの間を産褥期(さんじょくき)と言います。
大体この時期には、平熱が元の体温に戻ります。
ただ産褥期の女性はしっかり休んで、体の回復を第一に考える必要があります。
分娩時のダメージだけでなく、赤ちゃんのお世話でも身体に負担がかかるため、休めるときに休んで、無理をしない生活を心がけましょう。
家事や育児は完璧にこなそうとせず、家族と協力しましょう。
休めるときに、意識的に休息の時間を取ってください。家事は二の次にして、なるべく家族にお願いしましょう。
家族が難しいときは、家事代行サービスや地域の公共サービスを利用すると育児に集中できますよ。
体の早期回復を促すためにも、バランスの良い食事を心掛けましょう。授乳期は体力の消耗が激しいため、しっかり食事を取りましょう。
また、産褥期の産後ダイエットをしてしまうと回復するための栄養素が不足してしまうのでNGです。
産後は平熱だけではなく、熱がなくても、注意する点がたくさんあるのです。
では、具体的にどのように体調をチェックした方が良いのか1点ずつ見ていきましょう。
体重は約5週間で妊娠前の体重にもどる
お産により、あかちゃんや胎盤(たいばん)、羊水、血液などが体外に出るため、体重は平均5~6キロ減ります。
その後も少しずつ減少して、約5週間で妊娠前の体重にもどります。
また、産後1週間から10日くらいまでは、尿量とともに汗も増えます。
排便は、産後3~4日たってから出ることが多いです。胃腸のはたらきが鈍るため、便秘ぎみになってしまうこともあります。
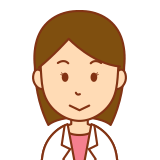
3日以上便通がなければ緩下剤(かんげざい)を使ってもよいでしょう。
子宮収縮は産後の経過を表す目安になる
子宮の収縮は、産褥の経過の良否を判断する大切なポイントとなります。
お産の直後、子宮はおへその下約3~4cmにあることが多いのですが、その後一時的に押し上がり、おへその高さぐらいになります。
それからは徐々に収縮し、約2週間でおなかの上から触れなくなります。
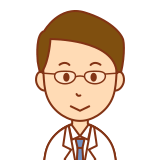
子宮の収縮は、経産婦のほうが初産婦より遅いことが多いですよ。
悪露は生理より量が多く、1か月ほど続きます。血が混ざった悪露や茶褐色の悪露が、産後6~8週間すぎても続いている場合や、量が増える場合には、医師に診察してもらいましょう。
子宮の回復の遅れなのか、胎盤や羊膜の一部が残っていないかなど、調べてもらう必要があります。
また産褥期には、内分泌系のはたらきが正常にもどっていないために、無月経が続くため、月経がありません。
授乳をしていない場合は、産後6~8週で月経がくることが多いようです。
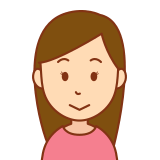
授乳している場合はそれより遅れるのよ。とても個人差のあるものなのね。
赤ちゃんに欠かせない母乳の状態もチェックしよう
赤ちゃんが大きくなるために欠かせない母乳の状態も確認しましょう。
個人差はありますが、だいたい産後2~3日で乳房がかたくなり、乳汁の分泌が始まります。
これを初乳と言い、黄白色の濃厚なものです。その後10日ほどかけて成乳になります。
ホルモンバランスの乱れなどで精神的に不安定になる
お産による疲労から、脱力感で無口になる場合や、逆にお産の喜びで、興奮したり多弁になったりすることがあります。
気分が落ち込んだり、落ち着かなかったり、涙が出たり、イライラするといったことがあります。
これは、ホルモンをはじめとする体の急激な変化と関係しており、ある程度はしかたのないことです。
ただあまりにもその症状が目立つ場合や、長くその状態であるときは、医師に相談しましょう。
平熱でも以上の部分に異変があるようなら、迷わず専門家に相談しましょう。
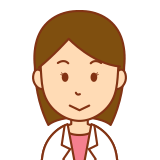
症状が軽いうちに処置してしまいましょう!
まとめ

- 出産直後から2週間程度、平熱が37度台になる
- 産後2週間以降、平熱が37度より下がらなかった場合、他の体の不調と合わせ、病状を確認する必要がある
- 38度台の発熱には注意が必要
- 産後になりやすい病気として「産褥熱」「乳腺炎」「腎う腎炎」があげられる
- 産後は平熱以外にも体の変化をしっかり見極める必要がある
- とくに産褥期は、休息を意識的にとる
産後、特に初産は初めてのことだらけで、不安になりがちです。体調も普段とは違うため、病院に行くタイミングで迷うこともあるでしょう。無理は禁物です。
特に産褥期は母体にとって大事な時期のため、37度以上あるなど迷ったら病院へ行きましょう。
ママやパパになったあなたの参考になれば幸いです。