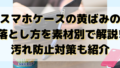あっ!弁当箱のパッキンにカビがついてる!?
弁当箱を見てパッキンにガビがいて驚いたことはありませんか?
この記事では弁当箱のパッキンについたカビを落とす方法と、予防策についてお伝えします。
最後にはカビ落としにおすすめな100均グッズと人気の弁当箱を紹介するのでぜひチェックしてくださいね!
私は毎日子供のお弁当を作っているのですが、何度か弁当箱のパッキンを外して洗うことを忘れてしまい気がついた時にはカビがはえていたことがありました。
弁当箱や水筒など湿気がこもりやすいところは、カビがはえやすいです。
ですが、掃除の仕方と予防策を覚えるとお気に入りの弁当箱を長く使うことができます。
この記事を読めばもう弁当箱のパッキンのカビで悩むことがなくなりますよ♪
弁当箱のパッキンにカビ!?落とす方法5選とは

弁当箱のパッキンについたカビを落とす方法はいくつかあります。
- 台所洗剤
- 熱湯をかける
- 酸素系漂白剤
- 重曹とクエン酸
- 塩素系漂白剤
またカビが表面だけの軽いものなのか、頑固なカビなのかによってもやり方が変わってきます。
これから紹介する方法は弁当箱のパッキンだけではなく、水筒やお風呂場などのパッキンのカビも落とすことができますよ!
カビ菌をそのままにしていたら食中毒のリスクも高まりますのでしっかり落としましょうね。
1つずつやり方と注意点をお伝えしますのでぜひ試してみてください。
1.台所洗剤
軽度なカビなら台所の中性洗剤で落とすことができます。
- 弁当箱のパッキンをはずす
- パッキンの部分に台所中性洗剤をつけて少し放置する
- スポンジや歯ブラシなどでカビの部分を軽く擦りお湯で洗い流す
- しっかり乾燥させる
私なら先にパッキンを外して洗剤をつけて端に置いておき、その間に他の洗い物を済ませて最後にパッキンを軽く擦り洗い流します。
その時に注意してほしいのは、カビを落としたいからと強く擦るとその傷からまたカビがはえてしまうので軽く擦るようにしてください。
2.熱湯
このやり方は1番簡単で用意するものも少ないのですぐに試すことができますよ。
- 弁当箱のパッキンを外す
- バケツやボウルに入れる
- 60℃前後の熱湯で90秒間洗い流す
多くのカビは熱に弱いため熱湯で落とすことができ、さらにカビの発生防止にもなります。
熱湯は熱いほどカビ落としにいいと思いがちですが、やかんで沸騰させたお湯をかけてはいけません。
熱すぎるお湯だとパッキンを傷めてしまう恐れがあるのでやめてくださいね。
またこのやり方はお風呂場で応用ができ、週に1度60℃前後のシャワーで熱湯をかけるとカビ対策にとても効果的です。
お風呂を出る時に冷水をかけるとカビが発生しづらいと聞いたとこはありませんか?
でも実際は冷水だと低温のため残った水分が蒸発しにくく、そこからカビが繁殖してしまいます。
私は冷水のやり方をTVで見てから実践していたのですが、逆に繁殖させていたのかもしれないです…。
今夜からは冷水をかけるのはやめて熱湯でやりたいと思います。
3.酸素系漂白剤
酸素系漂白剤は塩素系とは違いツーンとした匂いもなく、身体や環境に優しい洗剤です。
小さい子がいる家庭や子供のお弁当箱に安心して使うことができますよ。
- 酸素系漂白剤(過炭酸ナトリウム)
- 40℃〜50℃のお湯
- パッキンが入る大きさのボウルや桶 (アルミ製・金属製以外)
- ゴム手袋
酸素系漂白剤は、アルミ製・金属製に使うと黒ずんでしまうので注意してください。
ステンレス製であればに腐食に耐える性質があり鋳びにくいのですが長時間つける場合は避けてください。
また、酸素系漂白剤は手の皮脂を取る力が強いので、ゴム手袋がない場合はスプーンなどで混ぜるといいですよ。
- 弁当箱のパッキンをはずす
- カビをキッチンペーパーなどでそっと拭き取る
- 台所洗剤で洗い、すすぐ
- ボウルにゴムパッキンを入れる
- ゴムパッキンがかぶるぐらいのお湯(40℃〜50℃のお湯)を入れる
- 酸素系漂白剤を入れる(目安の量は、1リットルのお湯に対して約小さじ1)
- ゴム手袋を着用し軽く混ぜ、ゴムパッキンを沈ませる
- 30分〜3時間ほど漬け込む(3時間以上でも大丈夫です)
- 漬けている水を捨て、軽くこすりながら水ですすぐ
- しっかり乾燥させる
酸素系漂白剤は過炭酸ナトリウムを溶かすことで酸素が発生し、その力で漂白・消臭・除菌ができるのです!

漂白だけではなく、消臭・除菌ができるからついでに弁当箱をつけてもいいね。
4.重曹とクエン酸
先ほど紹介した酸素系漂白剤と一緒で環境や身体に優しい成分として重曹も人気ですよね。
重曹とクエン酸を混ぜてペーストを作り密着させてカビを落とすやり方です。
- 重曹(掃除用100g)
- クエン酸(小さじ1)
- 水
- 小さいブラシまたはヘラ
- ボウルや桶
- ラップ
- ゴム手袋
重曹とクエン酸は酸性の性質を持っていて、合わせると二酸化炭素を含む泡が発生します。
その泡でカビ汚れを浮かしてくれるのです。
- ボウルや桶に重曹とクエン酸、少量の水を入れてペースト状になるように混ぜる
- 弁当箱のパッキンをはずす
- カビをキッチンペーパーなどでそっと拭き取る
- 台所洗剤で洗い、すすぐ
- ブラシやヘラを使いカビの部分に先ほど混ぜたペーストを塗り、ラップで覆う
- しばらく放置したらラップを取り、ブラシで軽くこすりながら水ですすぐ
- しっかり乾燥させる
重曹やクエン酸は、漂白剤のように強い成分ではありません。
そのため、1回で落ちきれない場合は何度か繰り返してみてくださいね。
クエン酸がなく重曹のみでペーストを作る場合は、重曹と水を3:1の割合で混ぜて使ってみてください。
5.塩素系漂白剤
普段キッチン用の塩素系漂白剤(キッチンハイター、キッチンブリーチなど)を使っている人が多いと思います。
また、先ほどのやり方で落ちなかったカビがあったらこちらの方法を試してみてください。
- キッチン用塩素系漂白剤(キッチンハイター、キッチンブリーチ)
- パッキンが入るボウルや桶(金属製以外)
- ゴム手袋
塩素系漂白剤はステンレス製を除く金属性には使うことができません。
なぜなら酸化されて錆びやすくなってしまうからです。
酸素系漂白剤でもお伝えしましたが、ステンレス製を使う場合は長時間の使用を避けて下さいね。
- 弁当箱のパッキンをはずす
- カビをキッチンペーパーなどでそっと拭き取ります
- 台所洗剤で洗い、すすぐ
- ボウルにゴムパッキンを入れる
- ゴムパッキンがかぶるぐらいの水を入れる
- 塩素系漂白剤を入れる(ハイターそれぞれの規定の量)
- ゴム手袋を着用し軽く混ぜ、ゴムパッキンが沈むようにする
- 30分ほど漬け込む
- 漬けている水を捨て、軽くこすりながら水ですすぐ
- しっかり乾燥させる
塩素系漂白剤は漂白力が強いので、長時間の漬け込みは避けて用法を守ってくださいね。
また換気をしっかりして、酸素系のものと混ぜないように注意してください。
弁当箱のパッキンにカビを発生させないための予防策

パッキンがある弁当箱は密封性に優れている反面、弁当の湿気や汁気が付着しやすく、汚れが溜まりやすい部分でもあります。
そのため、雑菌が繁殖しやすいのでこまめな掃除と予防策で菌の繁殖を防ぎましょう。
今回ご紹介する予防策はこちらの4つになります。
- 毎回パッキンを外して洗う
- 泡スプレー洗剤
- アルコールスプレー
- 定期的に漂白除菌する
やり方をご紹介しますので、自分に合った方法を試してみてください。
毎回パッキンを外して洗う
私はこれができずに弁当箱にカビが生えてしまいました…。
やはり一番は衛生的に保つことがカビの発生を予防することなので、洗うたびに弁当箱からパッキンを外すことが大切です。
簡単なのですが、ゴムパッキンの溝まで綺麗に洗うのって大変ですよね。
ですが次の方法だったら弁当箱の細いパッキンの溝まで綺麗にすることができます。
泡スプレー洗剤
弁当箱のパッキンの溝ってとても洗いづらくないですか?
普段使っているスポンジでは細い溝に入らず綺麗に洗おうと思うと時間がかかってしまいますよね。
そこで私が毎日の弁当箱洗いに選んだのは台所洗剤の「泡スプレー」です。
今までの台所洗剤と違い、泡スプレーはスポンジがいらず泡の力で汚れを落としてくれるのが特徴です。
使い方としては弁当箱を洗うときにパッキンを外し、ふたの溝やパッキンにスプレーをして1分ほど置いておき、その間に他の洗い物を済ませて最後に洗い流せば完了です。
とても簡単でスポンジが届かないところも洗えて頑固な脂汚れも落としてくれるので、水筒を洗うときやフライパンの予洗いにも使えて便利ですよ。
アルコールスプレー
カビ掃除の後や毎日の洗い物の後にシュッと吹きかけるだけでも効果的で、速乾性があり、臭いを消してくれたりる効果もあるのでおすすめです。
これなら洗い物ついでにできるのでズボラな私でもできそうです。
アルコールスプレーで人気のパストリーゼなど、万が一口に入っても安全なものを選ぶといいでしょう。
定期的に漂白除菌する
カビ掃除でもお伝えしたパッキンを漂白除菌する方法です。
この方法は休日など時間がある時につけおきするだけなので取り入れやすいと思います。
私は弁当箱のパッキンのために漂白剤を作るのは面倒なので、大きめの桶やボウルに漂白剤を入れて弁当箱だけではなくコップや水筒もついでに付けおきをしていますよ♪

弁当箱のついでに他の食器も綺麗にできて嬉しいわ!
弁当箱のパッキン掃除には100均ブラシがいい

毎日弁当箱や水筒のパッキンを外して掃除するのって大変ではないですか?
私はキッチングローブをして洗い物をしているのですが、グローブをしたままだとパッキンを外せなくて困りますし、細かい溝をスポンジで掃除するのには苦労します。
そこで100均でパッキンを外すこともできる掃除ブラシを2つご紹介します。
●「パッキン外せる!キッチンブラシ」ダイソー

ダイソーの「パッキン外せる!キッチンブラシ」は全長約17㎝で、1本を2つに分けることができます。
白い方がブラシ・ピックになり、青い方がピンセットとして使える便利なアイテムです。
ピック部分は、弁当箱のパッキンの下に差し込んで持ち上げると簡単に外すことができます。
また、長いパッキンにはピンセット部分で挟んで持ち上げることができ、ブラシはカーブがついていて弁当箱の溝やパッキンの溝掃除に便利ですよ。
今回はダイソーのみで発見したのですが、ネット検索によると他の100均でも同じような商品が売られていました。
調べたところ、セリアでは下記の商品が人気のようです。
●「2way お弁当洗いブラシ」セリア
全長約13㎝で、裏側にブラシから外せて使えるピックが付いています。
ブラシは細くて弁当箱の溝にしっかりフィットしてくれます。
ピック部分は先が耳かきのようになっていてパッキンの下に入れると簡単に外すことができます。
しかもこのブラシは上部に丸い穴があり、フックに引っ掛けることができるので気がついた時にサッと使えて便利ですよ!
100均には他にもパッキン掃除に使えるブラシが売っていましたので、悩んでいる方は見てみてくださいね。
弁当箱のパッキンなしタイプと一体型がおすすめ


もう毎回パッキンを外して掃除するのは嫌だ!
私のように毎回パッキンを外して洗うのが面倒な方におすすめの弁当箱があります。
それは「パッキンなしの弁当箱」と「パッキン一体型の弁当箱」です!
それぞれ100均で実際に購入してみましたのでご紹介いたします。
●お弁当箱チューリップL(セリア)

こちらはセリアで購入した、パッキンなしの弁当箱になります。
- 商品名:お弁当箱チューリップL(セリア)
- 価格:110円(税込)
- サイズ:約163✖️121✖️48Hmm
- 内容量:650ml
- 電子レンジあたためOK(フタをずらしてご使用ください)
- 仕切り付き
- 食器洗浄乾燥機NG
横からカパッと開けることができ、タッパーみたいな弁当箱になります。
私が行った店舗にはシンプルなものからナチュラル系の柄が多かったです。
パッキンなしなので、漏れてしまうのではないかと気になりますよね。
そのため水を中に入れて漏れるのか検証してみました。

少しぐらい傾いただけではこぼれませんでしたが、垂直にしていると少し水滴が落ちてくるようでした。
大人が使う分には傾けないように意識すれば大丈夫だと思いますが、子供に持って行かせるとなると少し心配です。
その時は汁気が少ないおかずにしてあげるなど工夫すれば十分子供でも安心して使えると思います。
それでもやっぱりパッキンがないと不安な方はこちらがおすすめです。
●保存容器としても使えるお弁当箱 (ダイソー)

こちらはダイソーで購入したパッキンが一体型になっている弁当箱になります。
- 商品:保存容器としても使えるお弁当箱 (ダイソー)
- 価格:110円/220円/330円(全て税込)
- 内容量:300ml/500ml/950ml
- 電子レンジあたためOK(エア弁を開ければフタしたままOK)
- 仕切り付き
- 両面ロックでしっかり閉まる
- 食器洗浄乾燥機NG
- オーブンNG
大きさが3種類あり、ホワイトのシンプルな弁当箱です。

特徴はエア弁がついているのでレンジの時はフタを外さずにでき、パッキンがついているので漏れの心配もなく、外さなくていいところです。
こちらも漏れないか水を入れて検証してみました。

横にしただけでは漏れることはなく、逆さまにしてもエア弁部分から水が出ることはなかったです。
お弁当を振ることはないと思いますが、試しに少し振ってみるとしずくが落ちる程度でした。
この弁当箱は保存容器としても使えるので、汁気の多い煮物やカレーなどの保存にいいと思います。
まとめ

- 弁当箱のパッキンのカビが軽度なら台所洗剤や熱湯で落とすことができる
- 塩素系漂白剤を使いたくない人は、重曹とクエン酸を混ぜたペーストを塗るか、酵素系漂白剤でカビを落とすことができる
- 重度のカビの場合は塩素系漂白剤を使って落とす
- 弁当箱のパッキンのカビを発生させないための予防策は、毎回パッキンを外して衛生的に保つこと
- 休みの日などに漂白剤につけたり、洗い物終わりにアルコールスプレーをしたりするのも効果的
カビを発生させないためには衛生的に保つことが大切なので、こまめの掃除としっかり乾燥させるようにするといいと思います。
もうパッキンのカビで悩みたくない方には、パッキンがついていない弁当箱やパッキンが一体型になっている弁当箱に買い換えるのがおすすめです。