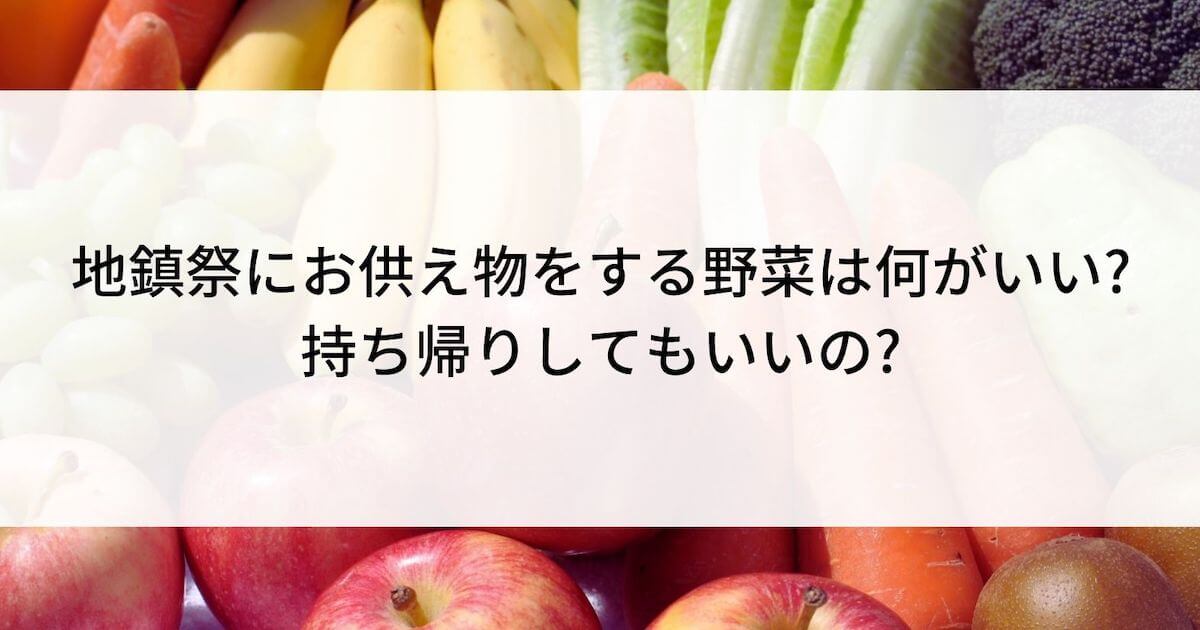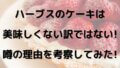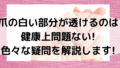地鎮祭で野菜を用意するように言われたけれど、どんなのがいいのかな?
地鎮祭とは基礎工事を始める前に土地の神様を祭り、工事の安全を祈願する祭りのことです。
地鎮祭では施主がお供え物を準備するのが一般的です。
お供え物の中に「三つの幸」というものがあり、その中の一つが野の幸の野菜になります。
ですが、どんな種類の野菜をどれぐらいの量を用意すればいいのでしょうか?
野の幸は、トマトやきゅうりなどの地面の上にできる野菜と大根や芋などの地面の下にできる野菜を2〜5種類ずつ、個数は1〜5個ずつ用意しましょう。
この記事では地鎮祭にお供え物をする野菜についてご紹介いたします。
新築を建てる時だけの珍しい行事なので知らないことも多く不安になりますよね。
地鎮祭は家が完成した後も末長く繁栄するように願う意味もありますので、この記事を読んでお供え物の野菜をしっかり準備しましょう!
地鎮祭にお供え物をする野菜は季節のものがいい


地鎮祭でお供えする野菜の準備をよろしくお願いしますね。

え!?野菜ですか?何を用意すればいいのかしら…。
「地鎮祭にお供え物をするための野菜」と言われてもどんな種類を用意するか悩みますよね。
野菜はその土地で採れたものや季節のものを用意するといいでしょう。
でもその土地で採れたものって言われても初めて住む土地だとわからないですよね。
基本的には地面の上にできる野菜と地面の下にできる野菜の2種類を用意してください。
- トマト
- なす
- きゅうり
- ほうれん草
- キャベツ
- ささげ など
用意する数は2〜5種類で、個数は1〜5個でその中に葉物野菜を1種類は入れたほうがいいでしょう。
ささげというのは、ささげ豆のことで昔から縁起を担ぐお赤飯にもよく使われていたそうです。
お供え物は神様に捧げるものですので、名前からしてぴったりな食材ですよね!
スーパーでも売っているところがあるそうなので、気になるかたは探してみてください。
私の近くのスーパーでは小豆と同じコーナーに置いてありました。
また、ニラやネギ類は臭いがするので地鎮祭のような神式では選ばないようにしましょう。
- にんじん
- 大根
- 芋
- かぼちゃ など
用意する数は2〜3種類で個数は1〜5個用意するといいでしょう。
お供え物は地域や規模によって数が変わることもありますので、建築会社や工務店の人に確認することをおすすめします。
もし迷ったら地鎮祭の後にいただくことを考えて、料理しやすい野菜を選ぶと決めやすいと思いますよ♪
地鎮祭のお供え物セットを用意するならこの7つ

地鎮祭で施主はお供え物と初穂料を用意することが多いそうです。
ですが、初めて行う地鎮祭でお供え物は何を用意したらいいのかわからないですよね。
お供え物セットはこの7つを用意するといいでしょう。
- 清酒
- お米
- 塩
- 海の幸・乾物
- 山の幸
- 野の幸
- 水
また、お供え物を神主さんや建築会社の人が用意してくれるところもあるので確認しておくといいでしょう。
1 清酒
一升(一升=1.8リットル)のお酒に祝儀用の熨斗(のし)をつけるのが一般的です。
地鎮祭を行う神社によって用意する量が違いますので確認をしてから用意するといいでしょう。
酒屋さんで「地鎮祭用の清酒をください」と言えば蝶結びの熨斗(のし)をつけてくれますよ。
熨斗の表書きは、上段に「奉献」で下段は「施主の名前」となるように用意してください。
縁起物として「祝儀樽」または「角樽(つのだる)」という慶事やお祝い用の樽を使うところもあるそうですよ!
私ならせっかくの祭事なので角樽で用意して記念に飾っておきたいです。
また神社によっては日本酒の瓶を2本用意し、紐でくくって角樽に似せてお供えするところもあるそうです。
2 お米
お米は一合(180cc)で洗米したものを用意するようにしてください。
前日にお米を洗い、ザルにあげて水切りしたものをキッチンペーパーや布の上に広げて一晩乾かしておきます。
以前は肥料に糞尿を使っていたので洗って清めていたようですが、最近はそのような肥料を使うことがないので洗わずにそのままでもいいそうですよ。
3 塩
塩は一合(100g)ほど用意するといいでしょう。
塩の種類には特に決まりはないので、自宅にあるものでいいと思います。
一部を平瓦(ひらか)に入れ替えてお供え物として、そのほかは敷地を清めるために使われます。
4 海の幸・乾物
海の幸は魚介類と乾物を用意するのですが、魚の種類に困りますよね。
「おめでたい」として鯛が代表的ですが、尾がついている魚であればなんでもいいそうなので好きな魚を用意しましょう。
乾物でおすすめなのは、縁起物としてよく使われる昆布・スルメ・ワカメを用意するといいでしょう。
昆布は「喜ぶ=よろこんぶ」としてよく知られていて、そのほかにも「広い布」の意味もあり「広がる=繁栄していく」という意味があるそうです。
スルメは結納の時にも使われ、お祝いの時には「寿留女」と書きその字から家庭円満などを意味しています。
ワカメは「若目」や「和布」とも書き、広がることの象徴として縁起がいいとされているようです。
乾物で迷ったらこの3つを用意しておけば安心ですね。
5 山の幸
山の幸は季節の果物をお供え物として用意するのが一般的ですが、りんご・オレンジ・バナナなど一年中手に入る果物をお供えする人が多いようです。
種類や個数は地鎮祭の規模や地域によって異なりますが、3〜5種類の果物を1〜5個ずつお供えするようです。
また、果物の代わりにきのこ類をお供えするところもあるそうですよ。
6 野の幸
野の幸は、トマトやきゅうりなどの地面の上にできる野菜と大根や芋などの地面の下にできる野菜を2〜5種類ずつ、個数は1〜5個ずつ用意しましょう。
ほうれん草やキャベツなど葉のものを1種類入れるといいそうです。
お供えする時は三方(さんぽう)という台の上に乗せて祭壇に飾りますので、小ぶりの野菜がいいと思いますよ。
7 水
水は一合(180cc)を用意し、水道水やミネラルウォーターでいいそうです。
水は水器(すいき)という容器に入れてお供えします。
また施工会社や神社の人に聞けば、その地域のお供え物について教えてくれるので一度聞いてみるのもいいかもしれません。
ネットで「お供え物セット」と検索すると、お酒だけのセットや乾物だけのセットが売っているので迷ったら通販サイトで購入するのもいいと思います。
ネットで頼む際は地鎮祭に間に合うように届く日を確認しておくといいでしょう。
地鎮祭のお供え物を持ち帰りありがたくいただこう

地鎮祭が終わり、その後お供え物はどうするのでしょうか。
お供え物を誰が準備するのかでも違ってきますし、実際に行った人でも様々な意見があるようです。
結論から言うと地鎮祭のお供え物は施主が持ち帰ります。
ですが神主さんが全て持ち帰ったという人もいれば、施主である自分達が持って帰ったという人もいてどうすればいいのか悩みますよね。
以前は地鎮祭の後に直会(なおらい)という食事会があり、お供え物を参加者で頂きました。
しかし最近は車を運転して帰る人や工事作業に取り掛かる人などに配慮して、直会を行わないことが多いため、持ち帰ることが一般的になっています。
お供え物に関して考え方は様々で、お供えをした時点で神様に食べられたと考えるので明確に誰が持ち帰るなどのルールや決まりはありません。
そのため、お供え物を準備したり神主にお供え物の分も込みで初穂料を渡していたりすると施主が持ち帰るのが一般的な考えのようです。
また神主さんが持ち帰りした場合は、神社に奉納するようです。
わからなければ建築会社の人に聞いたり、神主さんの方針に合わせたりすれば問題ないでしょう。
お供え物を持ち帰った場合は、処分はせずに神様からのお下がりとしてありがたくいただきましょう。
お供え物の決まった食べ方はありませんが、昔は火事を連想させるからと焼いてはいけないなど言われていたそうです。
ではお供え物はどうやって食べるのがいいのでしょうか。
お供え物の食べ方
<お米>
地鎮祭でお供えしたお米は土地の四方の方角に撒き、残ったものは持ち帰ります。
普通に炊いて食べてもいいのですが、ささげ豆と一緒にお赤飯にするといいですよ。
<海の幸・乾物>
地鎮祭では尾がついている魚を用意するのですが、食べるためには鱗を取ったりしてうまく処理をしないといけませんよね。
でも私のように魚の下処理ができない人はどうすればいいのでしょうか。
そこで調べてみるとスーパーや魚屋さんでお金を払えば処理をしてくれるお店があるようなので、困ったら問い合わせてみるといいですよ。
食べ方は生で食べる刺身が一般的ですが、真夏など気温が高い時期に行った場合は火を通して食べたいですよね。
そんな時は焼くのではなく蒸したり煮たりして食べるのがおすすめです。
鯛の場合は煮付けでもいいですし、お供え物で使ったお酒と昆布で酒蒸しにてもいいと思います。
<山の幸>
フルーツは料理せずそのまま食べるのがいいでしょう。
きのこ類の場合は、野の幸の野菜と一緒に煮物などの料理で使って食べましょう。
<野の幸>
野菜の食べ方は、筑前煮などの昔から日本でおめでたい時に食べられていた料理にするといいでしょう。
また季節の野菜でしたら蒸して温野菜にして食べるのも美味しいと思います。
まとめ

- 地鎮祭にお供え物をする野菜はその土地で採れたものや季節もので、地面の上できる野菜と地面の下にできる野菜を種類は2〜5種類ずつで個数は1〜5個ずつ用意する
- お供え物をする野菜の数と種類は、地鎮祭を行う地域や規模によって違うこともあるので施工会社や業者に確認するといい
- 鎮祭のお供え物は施主が持ち帰って食べるのが一般的だが、神主が持ち帰り神社に奉納する場合もある
- お供え物セットとは「清酒、お米、塩、海の幸・乾物、山の幸、野の幸、水」のことである
- お供え物を持ち帰った場合は、処分はせずに神様からのお下がりとしてありがたくいただきましょう
地鎮祭はその地域や規模、行う神社によって異なることが多いので、気になることがあれば事前に施工会社や神主さんと打ち合わせしておくといいと思います。
地鎮祭のお供え物は施主が持ち帰り、神様のお下がりとして家族でありがたくいただきましょう。