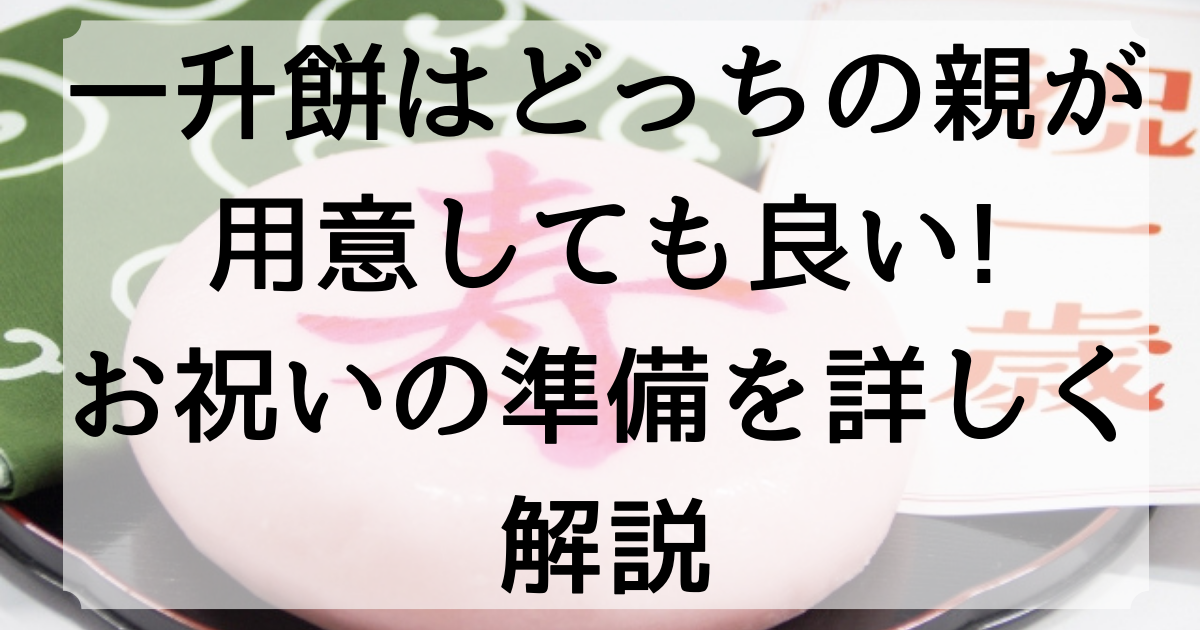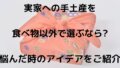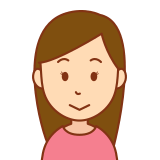
うちの子もうすぐ一歳のお誕生日だね、一升餅って誰が用意するものなの?
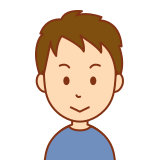
うちの親にはまだ聞いていないけれど、ママの親は何か言っていた?
一升餅をどっちの親に頼んでも大丈夫です。一般的に特に決まったルールがあるわけではないので、用意できる方にお願いしても良いです。
この記事を読むと実際にお祝いをした方の体験談を知ることができます。
ご家庭ごとに場所選びやお祝いに参加する人数が違い、そういうやり方でもできると気づくことができます。
心がこもった両親へのおもてなしや気遣いも少々必要になってきます。良い思い出に残るようお祝いの準備方法をお伝えします。
一升餅はどっちの親が用意しても良い!準備の方法

一升餅をどっちの親に手配しもらっても良いです。はっきりとしたルールはありません。
一升餅を用意してあげたい気持ちの確認が取れれば、気軽に頼めますね。
お子さまのお誕生日が近づいてきたら、一度どのように考えているかどっちの親にも確認を取りましょう。
一緒にお祝いを考えているかどうかも聞けるとこの後の予定が立てやすいです。
では、どのような考え方で計画していったら良いのかですが、親がお祝いに来る時にどんなものに費用が掛かるのか見ていきましょう。
- 一升餅代
- 交通費(飛行機代、高速代、ガソリン代、電車代)
- 宿泊代(泊りがけの場合)
- お祝い金
- プレゼント代
- 当日の食事代
- 場所代(場所を借りる場合)
- 写真代(スタジオなどで撮る場合)
お祝い事なのでお祝い金を用意して来られたり、プレゼントを持って来られたり何かしら用意されてくるでしょう。
あとはそれぞれが住んでいる場所によって、交通費が高くなる場合があります。交通費も考慮しておきましょう。
以下の内容を参考に、二人の両親の状況を確認してみましょう。
- どっちかの親が近くに住んでいる場合・遠くに住んでいる場合
- どっちの親とも来ることができる、もしくは片方の親だけ来ることができる
- どっちの親も来られない(介護が必要、入院中など)
ケースバイケースですが、考え方としては旅費代のことやスケジュール等も含めて参加できるかなど、確認しておくと計画しやすいです。
- 遠くに住んでいる場合には、移動時間と交通費が掛かる
- どっちの親とも参加できる場合には、全員集まれるので一緒に食事もお祝いもできる
- 片方の親だけ参加できる場合には、来られない親に後日お祝いした報告を入れておくこと
- どっちの親も来られない場合には、すべて自分達のスケジュールでお祝いできるが、後日どっちの親にも報告を入れると喜んでもらえる
ご家庭の状況に合わせてどっちの親にも気配りが必要です。親には無理のない範囲でお祝い行事に参加してもらえれば、自分達も安心できます。
孫が生まれるとなにかと金銭面で親にも負担がかかってしまいます。出産祝い・100日祝(お食い初め)・初節句などお祝い事がしばらく続きます。
費用に対しての考え方は、実は親の出費が多くなっているケースもあります。
実親には相談しやすいのでついつい頼みがちでしょうが、出費合計が片方の親だけに偏らないように気をつけておきたいです。
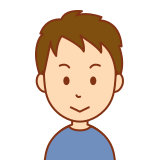
どちらの親からも一升餅を買うよと言われなかった
その場合には、自分たちで用意してあげても良いでしょう。
一升餅は手作りすることができます。2kgのもち米を用意してホームベーカリーにセットしてください。
お餅をついて楕円形もしくは小さい丸型をたくさん作りましょう。小さい形にしておくと食べやすいです。
購入する場合は、和菓子屋さんやお米屋さん、デパートや通販サイトなどで買うことができます。
一升餅のお祝いをどこでやるのか場所決めをしよう
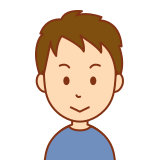
どこでやるのがいいのかな?
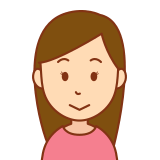
子供のご機嫌を考えると、慣れている自宅でやる方がいいな?
お祝いをする場所として考えられるのは次の3つです。
- 自宅にご両親を招く
- どこか座敷のあるお店を予約する
- ご両親の家に行く
<自宅にご両親を招く場合>
自宅に親を招待してお祝いしたい場合には、お子さんが一番慣れている場所なので、ぐずってもなんとかなります。
あとは部屋の飾りつけなどをして、お料理やケーキなど食事の準備をどうするか考えておきましょう。お子さんの好きなメニューがいいですよね。
お料理はお取り寄せなど組み合わせても時短できます。部屋の飾りつけやセッティングなどは是非パパにも手伝ってもらいましょう。
私が一歳のお祝いで両親を招いた時に天ぷらを揚げましたが、慌てていたのか手に火傷をしてしまいました。
接待に追われ、手の甲に油がはねても冷やす余裕がありませんでした。今でも苦い思い出です。
接待するのは体力的にもくたくたになりがちです。メンタル面にも気をつけながら準備してください。
<どこか座敷のあるお店を予約する場合>
お子さんのことを考えると、お座敷があるお店が理想ですね。この場合、一升餅を扱っていないお店であれば、お店に了承を得て持参しても良いでしょう。
もし食事代を折半でお願いしたい場合には、お店を予約した段階で折半にしたいことを伝えれば、多少言いやすいかと思われます。
<ご両親の家に行く場合>
実家が近い理由で実家に呼ばれるバターンが予想されます。この場合にはお子さんのぐずった場合の対処法を用意しておくと良いでしょう。
お料理や一升餅の準備は誰がするのか事前に打ち合わせをして当日漏れのないようにしておきましょう。
では次に、経験された方々の例を参考に場所決めの考え方について見ていきましょう。
| 親の住んでいる場所 | 場所 | 様子 |
| 両方とも近く | 近くの個室料理屋を予約 | 五月人形・ケーキ・一升餅をお店の了承をいただいて持ち込んだ |
| 旦那さんの実家(義親)が遠い、自分(実親)の親は近い | 実親のみ自宅に招待 | 当日、旦那さんの実家とテレビ電話をつないだ |
| どちらも遠い | 自宅に招待 | 手料理でおもてなしをして、餅踏みと選び取をして祝った |
| 両家とも近い | 旦那さんの実家 | 義親が料理やケーキなどを手配してくれていた |
| 旦那さんの実家(義親)が遠い、自分(実親)の親は近い | お店 | 旦那さんの親も遠くから来てくれて一緒にお店で食事をした その後、自宅へ行きケーキ・一升餅・選び取りをして祝った |
| どちらも近い | 自宅 | 両方の親が料理を持参し、一升餅はママ側の親が準備した |
| 自分(実家)の親が遠く、旦那さんの実家(義親)の親は近い | 自宅とお店 | 昼間はスタジオで写真を撮り、自宅でパーティーをして、夜はお店を貸し切って親戚も集まりお祝いした |
ご家庭の数だけお祝いの仕方がありますね。自分の場合はどうすると喜ばれるか、どっちの親とも相談して決めるのが良さそうです。
一升餅はどっちの親も知っている方法を聞いてみよう
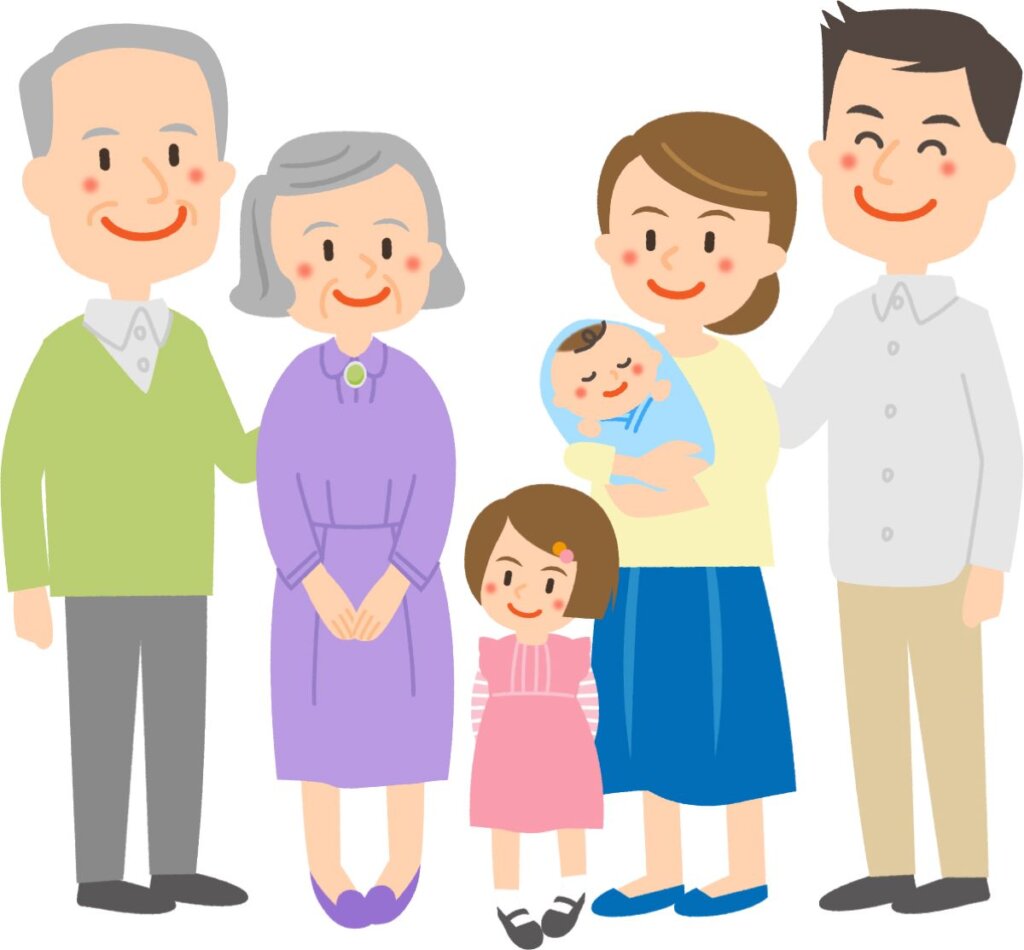
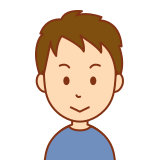
一升餅のお祝いってどうやるの?
地域ならではのしきたりや風習があるかもれしないので、どっちの親にも一升餅のお祝いについて方法を尋ねてみましょう。
さらに親がお祝いはどうするの?と聞いてきたら、是非相談してみてください。
- 昔はこうだった
- あなたの時はこうしたよ
- この地域ではこういうしきたりがあるよ
- ○○くん(○○ちゃん)に一升餅用意してあげたいと思っている
最後の「用意してあげたい」という気持ちが聞けたら、ありがたく気持ちを受け取りましょう。
どっちの親からも用意してあげるよと言われたら、嬉しいですね。ですが、一つで十分ですので、どちらかには角が立たないよううまくお断りを入れましょう。
大変ありがたいのですがお気持ちだけいただきますとていねいに伝え、その代わりに別のものを提案してみましょう。
プレゼントでも嬉しいとうまく伝えて、どっちの親の顔もつぶさないように心配りをしておきましょう。
しきたりや風習を気にするタイプ?地域で様々違いあり
一升餅のお祝いは日本全国で昔から行われています。では、そもそもどんなお祝いなのでしょうか。
<一升餅のお祝い>
- 一升餅の一升(いっしょう)とお子さんのこれらかの人生(一生)を掛け合わせている
- 一生食べ物に困らないで生きていけるよう願いが込められている
- 健やかに成長してほしい願いを込めて行うお祝い行事
- 昔から親から子へ受け継がれてきた行事の一つ
- 一般的には、風呂敷を使い一升餅を包んで斜め掛けにし、お子さんに背負わせる
- 歩けても歩けなくても良い
歩けなくても縁起が良いとされています。重くて泣いてしまう子が多いでしょうが、良い思い出になります。
昔、ある地域では一歳の誕生日前後から早く歩き出すと、家を離れるので良くないという言い伝えがありました。
わざと重いお餅を背負わせて、歩きを止めさせようという考えです。地域によって祝い方が異なりますので、風習を確認しておくと方法がわかります。
| 転ばせ餅 (東北・北海道の一部) | 赤ちゃんの足にお餅をぶつけて歩けなくする | 転ぶと厄落としになる |
| ぶつけ餅 | 赤ちゃんの足にお餅をぶつけて歩けなくする | 立てないと家に長くいてくれる |
| 踏み餅(九州) | 地にしっかりと足をつけて生きていけるようにする | 素足やわらじを履いた足でお餅の上に立たせる |
地方ならではの風習があって面白なぁと思います。私の場合は関東で、風呂敷に一升餅(実母が和菓子屋さんで購入)をくるんで、背負わせる方法でお祝いしました。
長男は重くて立てず、ハイハイの姿をして涙していました。その後はみんなで写真撮影をしました。
特徴のあるお祝い方法だとひときわ思い出に残りますので、取り入れるのも良いしょう。
誕生日を楽しみたい!選び取りで盛り上がろう
一升餅の他にも一歳のお祝いでやる「選び取り」という行事があります。お子さんの将来の職業や才能を占うもので、実物を並べて赤ちゃんに取ってもらいます。
- そろばん(商才がある)
- お札や硬貨(裕福になる)
- 筆(学者や芸術家になる)
- 箸(食べ物に困らなくなる)
最初に「どれを選ぶか」や、「一番長く持っているアイテムはどれか」など、あらかじめ決めておくとスムーズです。
また実物を並べても良いし、「選び取りカード」を使ってもやっても楽しめそうです。どっちの親も楽しんで見守ってくれることでしょう。
一升餅はどっちの親も楽しみにしているお祝い行事!

どっちの親も孫の一升餅のお祝いが楽しみで仕方がありません。気持ちを受け取りましょう。
「目に入れても痛くないほど孫は可愛い」と良く言われる言葉を聞いたことはありますか?祖父母にとって、孫は可愛くて仕方のない存在なのです。
どっちの親も一升餅や一歳のお祝いを楽しみにしているでしょうから、丁寧に声掛けして気持ちを引き出せると安心です。
義親とは、実親よりもお付き合いが浅いですので始めは意思の疎通が難しいことも出てくるでしょう。
祖父母、父母そしてお子さん全員が楽しめるように一升餅の計画を立ててみましょう。どっちの親にとっても孫との楽しみが増える行事になります。
記念の残し方として、手形足形などやったり、ビデオ撮影やスタジオ撮影などをしたりすると良いですね。
- 手形・足形で思い出作り!(紙粘土や色紙など)
- 動画や写真を撮って後日お礼状と一緒にプレゼントすると良いでしょう
我が家では紙粘土で手形を取りました。もう17歳になりますが、まだその紙粘土は壊れずに飾ってあります。わりと長持ちしていますよ。
もしかしたらどっちの親からもお祝い金をいただくことになるかもしれません。事前にお返しを用意しておきましょう。当日渡せるとベストですね。
お返しは名入れのカステラやバームクーヘンなどが人気があります。決めづらい場合には、カタログギフトも喜ばれるアイテムですね。
まとめ

- 一升餅はどっちの親が用意しても良い
- 自分達で一升餅を用意しても良い
- 一升餅の昔からのしきたりや風習を聞いて参考にしても良い
- どっちの親も自分たちもお子さんも全員が楽しめるように調整しながら計画する
- お祝いのお返しをあらかじめ用意しておく
お祝い行事は最終的にはご家庭で決めて良いものです。どっちの親の希望も叶えつつ、パパママの希望も入れられたら良いですね。
折り合いをつけることの方が多いかもしれません。お祝い行事の意味を知り、家族みんなで心を込めて行えればお子さまや全員にとっても良い思い出となるでしょう。