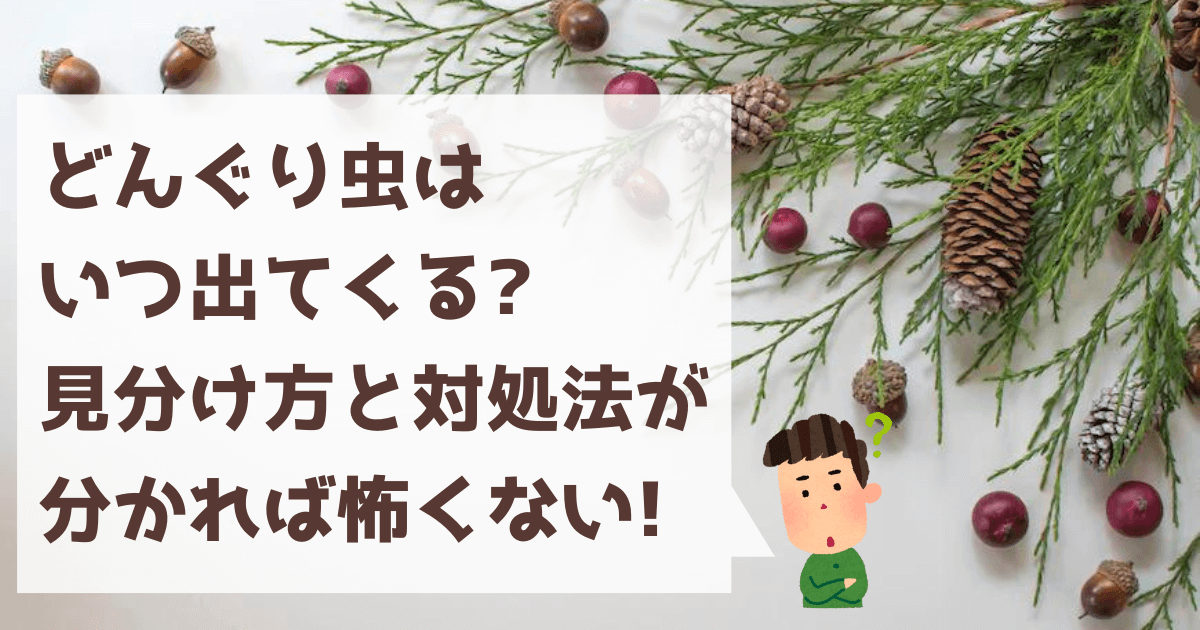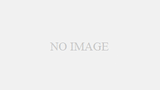こどもが拾ってきたどんぐりを保管していたら、変な虫が出てきた…!なんて経験をしたことはありませんか?
可愛らしいどんぐりから出てくる虫…。恐怖でしかないですよね。

分かるわ~。でも、どんぐりを拾わないで!とも言えないし…。

あの虫っていつ出てくるのかしら?それが分かればいいんだけど。
こどもが拾って大切そうにしているどんぐりって置いておいてあげたいですよね。
確かに虫がいつ出てくるのか分かればいいのですが、残念ながらいつ出てくるかは分かりません。
ですが、虫がいるどんぐりを見分ける方法があるのです。
この記事では、どんぐり虫の正体と虫に出くわさないための方法を分かりやすく説明します。
これを読めば、拾ってきたどんぐりはもう怖くない!
どんぐりにいる虫はいつ出てくるか分かるの?

拾ってきたどんぐりから虫がいつ出てくるかは分かりません。
拾った翌日に出てくることもあれば、3日後や1週間後のこともあります。
ここで私の友人の実体験についてお話しさせてください。
友人のお子さんがどんぐりを拾ってきたので、「今度工作に使おうね~」とジップロックにどんぐりを入れていました。
友人はどんぐり虫の存在を知っていましたが、1週間くらい様子を見て出てこなかったら大丈夫だろう、と思いジップロックに入れたそうです。
2.3日おきに確認していましたが一向に出てくる気配はなかったので、1週間後にどんぐりをお子さんに渡しました。
その後、お子さんは空き箱に入れて保管していたのですが、約2週間後に工作で使おうと箱を開けると、そこにはたくさんの白い小さな虫が…。
幸いしっかり閉まるタイプの箱だったので、虫は外に出ていなかったようです。
このように2週間以上経ってから、虫が出てくることもあります。
そのためこれだけ出てこないならば大丈夫だろう、というのは当てになりません。
そして、どんぐり虫は1cmにも満たないくらい小さいです。
万が一、家の中でどんぐり虫が出てきてしまったら、探すのは大変そうですよね。
特に人体に害はないことと、どんぐり以外に産卵することはないので、それ以上増えることはありませんが、気持ちのいいものではありません。
どんぐり虫は緑色のどんぐりに産卵します。そしてどんぐりが茶色に色づくころに出てくるのです。
そのため秋によくみかける茶色いドングリの中には、虫がいる確率が高いと言えます。

ひぇ~。こどもが拾うどんぐりには高確率で虫がいて、いつ出てくるかも分からない。じゃあどうしたらいいの?
いつ出てくるかは分かりませんが、入っているかどうかを見分ける方法はあります。
また虫が入っている場合でも、出てこないようにする方法もあるのです。次の項で詳細について説明しますね。
これらを実践することで、なるべく虫がいないどんぐりを選ぶことができます。
また万が一虫が入っていたとしても、遭遇して悲鳴を上げる、なんてことは避けられますよ。
どんぐりから虫が出てくるのはなぜ?対処法は?

なぜかというと、どんぐりに穴をあけて産卵する虫がいるからです。
どんぐり虫は何種類か存在します。どんぐり虫の種類や生態について説明しますね。
どんぐり虫の正体
どんぐり虫で多いのは「クヌギシギゾウムシ」「コナラシギゾウムシ」などのゾウムシです。
あと「ハイイロチョッキリ」や「蛾の幼虫」などもいます。
これらのどんぐり虫は成虫でも1㎝に満たない小さな虫です。
長い鼻のような口吻(こうふん)というものがあり、どんぐりに小さな穴を開けて中に産卵します。
なぜどんぐりの中に卵を産むのかというと、幼虫がふ化したあとドングリの実を食べて成長するからです。

じゃあ穴の開いたどんぐりはやめておいたらいいんだね!
産卵のときに開けられた穴はとても小さいため、目視で確認するのは難しいです。
しかもハイイロチョッキリは、卵を産んだ後でどんぐりの穴を埋めてしまうので分かりません。
卵を産んだ後、どんぐりの枝ごと切り落としてしまいます。
そのため「チョッキリ」という名前がついたようです。

名前だけ聞くとなんだか可愛い感じがするね。
そうですね。ゾウムシもゾウみたいだからこのような名前がついたようです。そう思うと少し興味深いですよね。
この本があれば、お子さんとどんぐり拾いをするときに、どんぐりやどんぐり虫について楽しく学ぶことができますよ。
どんぐり拾いがもっと楽しくなりそうですよね。
どんぐり虫の対策方法
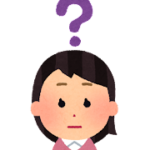
なぜどんぐりから出てくるのかは分かったけど、虫が出てこないようにする方法はないの?
あります!今から簡単にできる対処方法をお伝えしますね。
- 冷凍庫にいれる
- レンジでチンする
- 塩水にいれる
- 熱湯で茹でる
この4つの方法になります。詳しく解説するので、ご自身に合った方法を試してみてください。
冷凍庫に入れる
どんぐりを冷凍庫に入れることで、中の虫は凍ってしまって出てきません。冷凍する手順は以下になります。
- どんぐりをきれいに洗って、しっかり水気を切る
- ジップロックなどにいれて冷凍する
- 乾いた布の上にどんぐりを広げて、風通しの良い日陰で乾燥させる
冷凍する期間は1週間程度です。解凍は自然解凍にしましょう。
解凍しないまま工作などに使うと壊れてしまう可能性があるので注意が必要です。
レンジでチンする
どんぐりをレンジでチンして熱することで、中の虫を退治する方法です。
- どんぐりをきれいに洗う
- お皿にクッキングシートを敷き、その上にどんぐりを並べる
- レンジでチンする
チンするときは、600Wで20秒くらいずつから始めましょう。
チンしたどんぐりは結構熱くなるので火傷しないようにしてくださいね。
やりすぎると殻が爆発してしまうため注意が必要です。
また短い時間だとしっかり熱が通らず、中の虫が退治できているか分からないので、少し難しいかもしれません。
塩水に入れる
塩水に入れるだけでどんぐり虫は退治できます。
- どんぐりを洗って容器に入れる
- つかるくらい水を入れる
- ここに塩を入れて2日ほど置いておく
- 乾いた布の上にどんぐりを広げて、風通しの良い日陰で乾燥させる
このとき塩の濃度が3%くらいになるようにしましょう。

200mlの水なら6gだね。
少し手間はかかりますが、冷凍するより早く出来ますね。
熱湯で茹でる
最後は、熱湯で茹でる方法になります。個人的にはこの熱湯を使う方法がおすすめです。
- 鍋に水とどんぐりを入れる
- そのまま火をかけて沸騰させる
- 5~10分程度煮る
- 乾いた布の上にどんぐりを広げて、風通しの良い日陰で乾燥させる
沸騰したお湯にどんぐりを入れると割れてしまうこともあるので、水の状態からどんぐりを入れて火にかけるようにしましょう。
調理用のお鍋を使うのはちょっとなぁ、という場合は使い捨てのアルミ容器などでもできますよ。
以上がどんぐり虫が出てこないようにする方法です。
どの方法でもどんぐりはしっかり乾かしましょう。
濡れたままだとカビが生えてくる可能性があります。
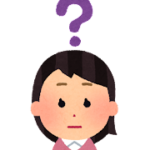
この方法ならどんぐり虫を見なくてすみそうだね。でも、そもそもどんぐりの中に虫がいるか見分ける方法はないの?
どんぐり虫がいるか、見分ける方法もありますよ。次の項で説明しますね。
どんぐりの中に虫がいるか見分け方を知ろう!

どんぐり虫がいるかどうかの見分け方は3つあります。
絶対ではないですが、この見分け方を使うことで高確率で見分けることができますよ。
虫がいるどんぐりを見分けよう
全部簡単にできるので、3つとも試してみることをおすすめします。
- 穴の有無を確認する
- 振ったときカラカラ音がする
- 水に入れる
どんぐりに開けられた穴は目視で確認することが難しいです。
ただし見えるような穴が開いていたり、ひび割れたりしている場合は、虫がいる可能性が高いのでやめておきましょう。
振るとカラカラ音がするどんぐりは、虫によって実を食べられているか、古いため実が小さくなっています。
穴や音に注意しながら拾って、持って帰ってきたどんぐりは水に入れるのが確実ですよ。
虫がいなくて実かぎっしり詰まっているどんぐりは水に沈み、反対に水に浮かぶどんぐりは虫が入っている確率が高いです。

じゃあどんぐりの処理で水を使うときに、浮いているどんぐりは取り除いて置いた方がいいね。
その通りです!処理する段階で浮いているどんぐりは除けている方が安心です。
これらはあくまでも目安です。虫がいても沈んでしまうこともあります。
また、どんぐりといっても色々な種類があります。
木の種類によってどんぐり虫がつきにくいこともあるのです。
コナラ、マテバヤシ、アラカシなどのどんぐりはどんぐり虫がつきにくいと言われています。
木に詳しい場合、これらの木の下のどんぐりを集めるといいですね。
これらの見分け方を参考にどんぐり虫のいないどんぐりを選びましょう。
その上で処理もしておくことをおすすめします。
どんぐりを使って工作をしてみよう
せっかく拾ってきたどんぐりを使って工作をしてみましょう♪
どんぐりを使って簡単にできるものを紹介します。
- どんぐりのやじろべえ
- どんぐりごま
- どんぐりを使ったお絵描き
- どんぐりマスコット
- どんぐりブレスレット
<やじろべえ>
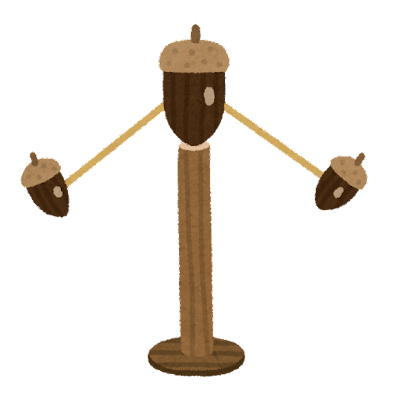
どんぐりを使った工作でやじろべえを思い浮かべる人は多いですよね。
そんなやじろべえは、3つのどんぐりと木の枝で出来ますよ。
真ん中のどんぐりは左右とおしりのところに、両サイドのどんぐりは左右ひとつずつに穴をあけます。
真ん中のどんぐりのおしりに短い枝をさしてください。
真ん中のどんぐりとそれぞれ両サイドのどんぐりを枝にさしてくっつけたら完成です。
手の上でバランスをとって遊んでみましょう。
<どんぐりごま>
どんぐりのあたまに穴をあけて、爪楊枝をさしたら完成です。
どんぐりの大きさや形によってそれぞれ違う回り方を見ることができますよ。
どのこまが一番長く回るか勝負するのも楽しそうですね。
<どんぐりを使ったお絵描き>
画用紙に絵を書いて、好きなところにどんぐりをくっつけましょう。
どんぐりを使うことでぐっと季節感が出ますよ。
普通のお絵描きとは一味違ったお絵かきを楽しむのもいいですよね。
<どんぐりストラップ>
どんぐりを顔に見立てて、目・鼻・口などを書いてみましょう。それをいくつか並べても可愛いですよ。
あたまに穴をあけて、金具と紐をつけたらストラップの完成です。

どんぐりをサンタ風にして、クリスマスのオーナメントにするのも良さそう!
<どんぐりブレスレット>
自分の手首に1周できるくらいどんぐりを集めましょう。
どんぐりのあたまとおしりに穴をあけます。紐を通してつないだらブレスレットの完成です。
どんぐりだけで作ってもいいですし、大き目のビーズを使っても可愛いですよ。
どの工作でも、どんぐりに穴をあける作業は必ずお父さん・お母さんがしましょう。
処理したどんぐりを使うことで、安心・楽しく工作できそうですね。
まとめ

- どんぐり虫がいつ出てくるかは分からない。茶色いどんぐりには高確率で虫がいる
- どんぐり虫にはゾウムシやハイイロチョッキリなどの種類がある
- どんぐり虫がいつ出てくるかは分からないが、虫がいるか見分ける方法はある。水に入れたときに浮くものにはいる可能性が高い
- どんぐり虫が出てこないようにする方法は冷凍する、塩水につける、レンジでチンする、沸騰させる、の4つがある
- 処理したどんぐりはやじろべえ、こま、お絵描き、ストラップ、ブレスレットなど工作で使うことができる
どんぐりから虫がいつ出てくるのかは分かりませんが、対処しておくことで安心してどんぐりをお家に置いておくことができますね。
せっかく処理したどんぐりなので、楽しく工作などで使うことができたらいいですね。
この本はカラフルで絵がたくさん出てくるので親子で楽しめること間違いなし!です。どんぐり拾いのお供におすすめですよ。