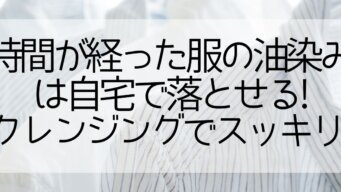 これなに情報
これなに情報 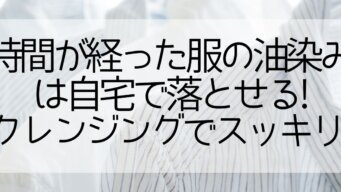 これなに情報
これなに情報 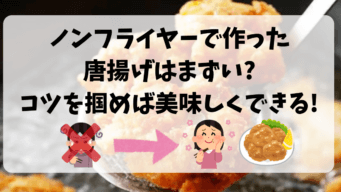 これなに情報
これなに情報 ノンフライヤーで作った唐揚げはまずい?コツを掴めば美味しくできる!
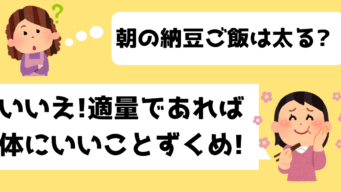 これなに情報
これなに情報 朝の納豆ご飯は太る?いいえ!適量であれば体にいいことずくめ!
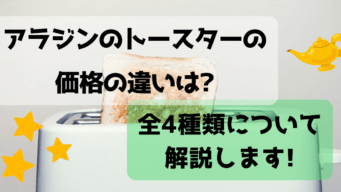 これなに情報
これなに情報 アラジンのトースターの価格の違いは?全4種類について解説します!
 これなに情報
これなに情報 グミを食べ過ぎて気持ち悪い!そんなときの対処法と目安量を解説!
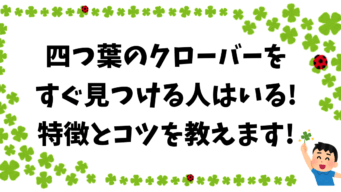 これなに情報
これなに情報 四つ葉のクローバーをすぐ見つける人はいる!特徴とコツを教えます!
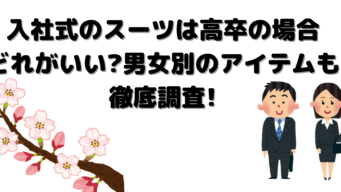 これなに情報
これなに情報 入社式のスーツは高卒の場合どれがいい?男女別のアイテムも徹底調査!
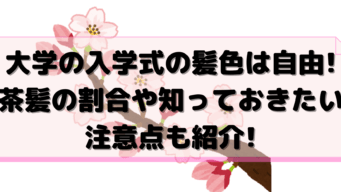 これなに情報
これなに情報 大学の入学式の髪色は自由!茶髪の割合や知っておきたい注意点も紹介!
 これなに情報
これなに情報 片思いでクリスマスプレゼントは重い⁉喜ばれる上手な渡し方!!
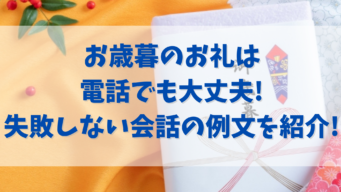 これなに情報
これなに情報